赤ちゃんの歯と口の健康は、将来の歯並びや全身の発達にも大きく関わります。「いつからケアを始めればいいの?」「どんなグッズや方法が本当に良いの?」と悩むママ・パパは多いものです。
私は歯科衛生士・口育士として30年以上の経験を持ち、3人の子どもを育てる母親としても日々学び続けています。
私の実体験をもとに、最新の研究成果や現場の声を織り交ぜながら、赤ちゃんの歯と口の健康についてわかりやすくお伝えします。
この記事では、最新の研究や現場の声、そして私自身のリアルな体験談を交えながら、赤ちゃんの歯と口の健康についてわかりやすくお伝えします。
赤ちゃんの歯と口の発達~知っておきたい基礎知識~
歯が生えるタイミングと個人差
赤ちゃんの歯は一般的に生後6か月ごろから生え始めます。
個人差ももちろんあります。ある相談に受診した赤ちゃんは3か月で生えてきた赤ちゃんもいました。
遅い赤ちゃんでは10か月を過ぎてやっと生える子もいます。
私の長男は5か月で下の前歯が生えはじめましたが、末っ子は8か月を過ぎるまで歯が生えず、健診でも問題ないと言われました。
この経験から赤ちゃん赤ちゃんの歯の生え方には大きな個人差があることを実感しています。
歯が生える前から始まる「お口の準備」
歯が生える前の赤ちゃんは、よだれが増えたり、口に指やおもちゃを入れて「カミカミ」する行動が目立ちます。これは、口腔機能の発達や顎の成長、唾液分泌の促進にとても大切な行動です。
脳の発達にも、なんでもなめたり、口にいれる行為は非常に大切です。
次男は生後4か月ごろから、手やガーゼ、そして安全な歯固めを口に入れて遊ぶのが大好きでした。冷蔵庫で冷やした歯固めを渡すと、機嫌よくカミカミしており、その様子を見ると成長を感じました。
歯が生える前から始める!お口ケアの新常識
歯が生えていなくてもケアは必要?
「歯が生えていないのにケアは早い?」とよく聞かれます。
実はお口に触れる練習はとても大切です。赤ちゃんは最初、口の中に指やガーゼが入ることに抵抗を感じる子が多いです。でも、毎日少しずつ優しく触れることで、歯みがきや歯科健診への抵抗が減ります。
また離乳食への飲み込みの促進にもつながります。
長男は最初、ガーゼを口に入れようとすると嫌がって泣いていましたが、お風呂上がりに「お口ピカピカしようね」と声をかけながら、ほっぺや唇をなでることから始めました。少しずつ慣れていき、やがてガーゼで歯ぐきを拭けるようになったのは、根気強く続けた結果です。
よだれの役割と日常ケア
赤ちゃんのよだれ(唾液)は1日1.5~2リットルも分泌され、お口の中を自然に洗い流してくれます。歯が生える前は、特別なケアは不要ですが、ミルクの吐き戻しや舌の汚れが気になるときは、湿らせたガーゼでやさしく拭いてあげましょう。
最初は唾液をうまく飲み込めずに、よだれとなってでてきます。離乳食が進みうまく嚥下が進むとよだれも徐々に減ってきます。唾液は食事と一緒にごくんと飲み込みます。
歯がため・お口トレーニンググッズの選び方と活用法
歯がための役割と最新グッズ
歯がためは、歯が生えるときのむずがゆさを和らげるだけでなく、顎や噛む力を育てるトレーニングにもなります。安全性や衛生面に配慮した歯がためを選びましょう。
形や色は様々ありますが、口に入る部分は平たく、薄い形態のものだと口を閉じるという唇のトレーニングになるのでおススメです!
色合いも大切です。赤ちゃんの目の神経や脳の発達に刺激を与えることができます。
また手と口の連動の動きの発達を促します。将来スプーンを口に運ぶなどの練習につながります。赤ちゃんが持ちやすい形を選んであげましょう。
ある患児さんは、リング型の歯がためをとても気に入り、歯ブラシのようにカミカミしていました。このおかげで、歯ブラシへの抵抗が少なく、歯みがきデビューもスムーズにはじめられましたとお母さんから報告をうけました。
歯ブラシを「歯がため」として使ってもいい?
歯ブラシを歯がため代わりに使う赤ちゃんも多いですが、必ず大人がそばで見守りましょう。安全プレート付きなど、誤飲防止設計のものを選ぶと安心です。
ただ汚れをとる歯ブラシは別に用意することをおススメします!
歯が生えたら始める!月齢別お口ケアの実践ポイント
生後6か月~:歯みがきデビューのコツ
歯が生え始めたら、仕上げみがき用のやわらかい歯ブラシを使い、1日1回から始めましょう。最初は「慣れること」が目標なので、短時間で優しく、機嫌のいいときに行うのがコツです。
またいきなりお口を触るのではなく、頬や唇を触りながら、徐々に口の中を触っていきましょう。
1歳~:自分みがきと仕上げみがきのバランス
1歳を過ぎると、自分で歯ブラシを持ちたがる子が増えます。この時期は「自分で歯みがき」と「大人の仕上げみがき」の両方を習慣にしましょう。
次男は、自分で歯ブラシを持つのが大好きで、遊び感覚で磨いていましたが、最後は『ママがピカピカにするね』と声をかけて仕上げ磨きをしていました。親子のコミュニケーションの時間としても大切にしています。
赤ちゃんの歯と口の健康を守る生活習慣
食事・おやつの選び方と虫歯予防
離乳食やおやつは、歯ごたえのある野菜スティックや甘くないおせんべいなど、よく噛むものを積極的に取り入れましょう。「食べたら水やお茶を飲ませてお口を洗い流す」ことも、虫歯予防に有効です。
我が家では離乳食の後期から、噛みごたえのある食材を積極的に取り入れました。
甘いおやつは控えめにし、野菜スティックやおにぎりを好んで食べてくれたのが印象的です。
おススメは柔らかくゆでた大きめのブロッコリーを手でむしゃむしゃくわえて、ツブツブの触感で口の発達を促してくれます。
家族みんなで虫歯菌対策
1歳半ごろからは、家族からの虫歯菌感染リスクが高まります。家族も定期的に歯科健診を受け、虫歯があれば治療しておきましょう。
次男の時期には、家族全員で定期健診とクリーニングに通いました。
そのおかげで3人の子どもたちは今も虫歯ゼロを維持しています。
赤ちゃんの口腔機能発達とマッサージの重要性
口腔機能発達の流れ
赤ちゃんは、母乳やミルクの液体を飲む哺乳嚥下から始まります。
離乳食の開始とともに、固形物を「食べる」「噛む」「飲み込む」機能が発達します。
この発達をサポートするために、口の周りやあご・口の中のマッサージが有効です。
この切り替えがうまくできないと、ミニトマトなどの誤嚥事故などの悲しい事故が起こってしまいます。
お口マッサージのやり方
- 頬を優しくぐるぐるマッサージ
- くちびるをちょんちょんつまむ
-
清潔な指で、歯ぐきとほおの内側を奥から手前へやさしくなでる
-
ほうれい線を伸ばすようにマッサージ
-
歯が生えたら、歯と歯ぐきの際もやさしくマッサージ
夜寝る前にほっぺやあごをマッサージしてあげると、とてもリラックスして眠りについていますと患者さんに言われたこともありました。
離乳食もよく食べ、歯みがきも嫌がらずに受け入れてくれるといいなあと思います。
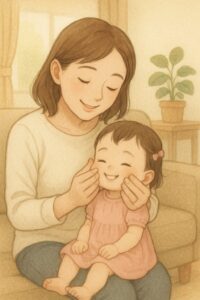
歯みがき嫌いを防ぐ!親子で楽しく続けるコツ
歯みがきタイムを「楽しい時間」に
-
歯みがきの歌や動画を活用する
-
ぬいぐるみやおもちゃで「歯みがきごっこ」
-
終わったらたくさん褒めてあげる
長男は「しまじろう」の歯みがき動画を見せながら歯みがきをすると、ノリノリで口を開けてくれました。また下の子は、歯みがき後に「できたねシール」を貼るのが楽しみで、毎日自分から歯みがきの時間を知らせてくれるようになりました。
よくある質問Q&A~現場で多い悩みとアドバイス~
Q. 歯みがきをどうしても嫌がるときは?
A. 無理やりではなく、まずはお口やほっぺを触る遊びから始めましょう。機嫌のいいときに短時間で終わらせ、終わったらたくさん褒めてあげてください。
Q. 歯みがき粉はいつから使う?
A. 歯が生え始めたばかりのころは不要です。奥歯が生えてきたら、フッ素入りの歯みがき粉を少量使い始めてもOKです。
Q. 歯みがきのタイミングは?
A. 毎食後が理想ですが、難しい場合は「夜寝る前」だけでもしっかり行いましょう。
まとめ
赤ちゃんの歯と口のケアは、歯が生える前からの「お口に触れる練習」や「歯がため」「お口マッサージ」など、最新の知見を取り入れながら進めていくことが大切です。私自身も三人の子育てで多くの失敗や悩みを経験しましたが、「無理なく・楽しく・毎日少しずつ」を意識することで、子どもたちも自然と歯みがきやお口ケアを受け入れてくれるようになりました。
これからも、赤ちゃんの成長や個性に合わせたケアを大切にしながら、家族みんなでお口の健康を守っていきましょう。疑問や不安があれば、ぜひ小児歯科や専門家に相談してください。
赤ちゃんの健やかな成長と、家族みんなの笑顔を応援しています。


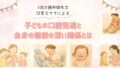
コメント