はじめに
仕上げ磨きのたびにギャン泣き――そんな日々に心が折れそうな親御さんへ。
私の家では、長男の仕上げ磨きがとくに大変で、毎晩「今日は絶対にいやだ!」と泣き叫ぶ声が響きました。何度も根負けしてしまい、「仕上げ磨きをもうしなくていいや」と諦めかけた日もあります。最後に寝顔を見て静かに涙が出るようなこともあり、親として自分の限界や弱さを痛感する体験でした。
歯科衛生士・口育士として多くの親子の仕上げ磨きに立ち会った体験をもとに、「子どもは仕上げ磨きをどう感じているのか」「乳児のお口はいつから触ってよいのか」といった疑問を、専門的かつ家庭のリアルな視点から一緒に考えてみましょう。
ギャン泣き仕上げ磨きの悩みは「誰も通る道」
自宅でも外来でも体感した「大泣きの日々」
「お母さん、今日も泣いちゃった」と診療室で涙ぐむお子さんの方をみる心配そうなお母さんを何度も見て、「うちの子も同じです」と心の中で話していたものです。実際、家庭では仕上げ磨きのたびに仰向けにして羽交い締め状態になることも……。泣きながら抵抗されて心も体もちょっと疲れた事も数知れず。「本当にこのやり方でいいの?」と悩むのは一度や二度ではないお母さんも多いはず。
ただし、この「ギャン泣き仕上げ」は特別なことではありません。90%以上のご家庭が体験しているという調査もあります。自分の子も含め、あらゆる性格のお子さんを診てきた私が言えることは「必ずギャン泣きは終わる時期が来ます!!」
自分でやりたい期・いやいや期の子どもの気持ち
仕上げ磨きを嫌がる主な理由は「自我の芽生え」いわゆる「イヤイヤ期」です。成長の証なのです。頭ではわかっていますが、忙しい子育てママには厳しい現実です。
それに加えて、お口の中はとても敏感。 「歯ブラシの当たりの方が不快」「冷たい感じが嫌」「一箇所がしみる」など、感覚面での抵抗も。
子どもは仕上げ磨きをどう感じているのですか?
専門家の視点:仕上げ磨きは「自由を奪われる時間」?
親としては「虫歯予防だからきちんとやりたい」と頑張るほど、子どもには「怖い」「我慢の時間」とも言えます。子どもにとっては、大人が歯みがきするタイミングで「自分の時間が中断される」「遊びが終わってしまう」と感じることがあります。
特に、「仕上げ磨き中の親の表情が怖い」と感じる子も多く、無意識に無表情や真剣な顔になりやすいのも一因です。虫歯にしたくないという親の一生懸命の現れなのは十分理解できます。
当事者体験談:お三人様、それぞれの「感じ方」
特に印象的だったのは、長男が毎回歯ブラシで触られただけで「痛い」「嫌だ、助けて」と涙ながらに本気で訴えたことです。どうしても仕上げ磨きをさせてくれない日は、お気に入りのぬいぐるみに先に磨く❛❜見せ磨き❛❜ごっこをして、「ぬいぐるみが頑張ったから次は僕だね」と順番でチャレンジしたのはとても効果的でした。嬉しかったです。
親に力が入りすぎると、それが子どもに伝わり「怖い」と泣き出すことも。科学的にも親の緊張状態が交感神経を刺激して、皮膚がこわばり、冷たくなり子どもは不安感を感じやすくなるという研究も発表されています。逆に穏やかに笑顔で歯みがきをすると副交感神経が優位になり、皮膚は温かく柔らかくなり子どもには安心感を与えることができます。
一方で、妹は初めて歯が生えた頃からあまり嫌がらずに磨かせてくれたタイプでした。お兄ちゃんがギャン泣きしているのを見て、逆に「私は泣かない」と言い張ることも多かったです。しかしきまぐれな性格なので、突然「今日は絶対仕上げ磨きしたくない!」とふてくされる日も。「じゃあ、ママと競争しよう!」と歯を磨く速さ比べをすると、素直に口をあけてくれるようになりました。
私自身も仕事や3人の育児の忙しさが重なると、気持ちの余裕がなくなり「ほら、早く口開けて!」と強い口調になってしまうこともありました。そんな日は、子どもが余計に泣き出して全く進みません。後から「ごめんね」と謝って、抱きしめながら気持ちを伝えると、次の日は驚くほど素直に磨かせてくれることもありました。❛❜親も完璧ではない、失敗があって当たり前❛❜ と、最近は自分自身に言い聞かせています。
休日は家族みんなで「歯みがきクイズ大会」を開催。「磨き残しがあると何が起こる?」「好きな歯みがきソングは?」などを出題しながら、ゲーム感覚でチャレンジ。大泣きしても最後は全員で「ナイスチャレンジ!」と褒めてあげると兄妹とも誇らしげな顔に。
こうした❛❜家族イベント❛❜ があると日々の仕上げ磨きもワクワクに変わりました。
ギャン泣き対策―どうしたらお互いラクになれる?
経験に基づいた実践的なコツ
専門家の立場からは「優しく声掛けして進めるのが理想」と言われますが、実際は「今日は子どもに歯みがきの順番を決めさせる」や「スタートからゴールまでをタイマーで競争遊びする」など、毎日少しずつ違う方法を工夫して取り入れていました。
失敗した日には「親も落ち込まず、家族全員でリセットできる習慣」を意識的につくるようにしていました。
姿勢を変えてみる(寝かせ磨き⇔向かい磨き)
実際、わが家でも「今日は立っちゃおうか!」と提案すると、意外と機嫌が直った経験があります。成長段階に合わせて、「どれがやりやすい?」と子どもの選択肢を考えた工夫も大切です。
歌や音楽で楽しい時間に
一度「歯みがき音頭」という自作の歌を家族で作り、仕上げ時間をまるでイベントのように演出してみました。最初は恥ずかしがるかと思いましたが、子どもがリズムを取りながら磨くことで泣き声が激減。続けているうちに「歌が始まると歯みがき」という習慣づけにも成功しました。
ごほうび・褒めることの重要性
我が家では普通のシールやご褒美では続かず、子ども自身が「今日泣かずに磨けた記念日」をカレンダーにシールで記録する【歯みがきチャレンジ表】を家族で作成。日々の達成が目に見えると、子どもも親も前向きになりました。
他にも「自分の好きな歌を選んで流して磨く」「終わった後に自作のごほうびスタンプカード」を作り、失敗した日も必ず「ナイスチャレンジ!チャレンジお疲れ様!」と声をかけるルールを徹底。本人の表情からも、だんだん仕上げ磨きを楽しめるようになってきたのが伝わってきました。
怒ったり、冷静に口をこじ開けたりしない
「丁寧にできなかった日があっても仕方ない」と割り切ることも必要です。 「羽交い締め状態」が続くことが、親も子もストレスがたまります。
親自身のストレスケアも重要
親自身が疲れて「今日は無理」と感じた日は思い切って仕上げをさぼることも。自分を責めずに家族の雰囲気を最優先する。「完璧主義を手放した」とき、不思議と子どもが素直に磨かせてくれる日がでてきました。
このような「親のメンタルリセット」も我が家特有の❛❜成功ポイント❛❜だったと振り返っています。
診療でも「泣いても大丈夫。大切なのは“続けること”」と伝えています。 「みんな泣いたり、嫌がったりしている」と思うと、少し肩の力が抜けるはずです。
乳児のお口の中、「いつから触っていいの?」―発達の流れ
赤ちゃんは生後1ヶ月半からお口を「感じている」
生後1〜2ヶ月ごろから、赤ちゃんは自分の指やこぶし、ガーゼなどを口に入れて「なめる」「吸う」「触れる」活動を始めます。
乳児へのお口ケアは「触れ合い」から始めるのがポイント
初めはガーゼや親の指で「歯ぐきや唇、舌を優しくなでる」でOK。ゆっくり口の中をこじ開ける必要はありません。
歯科衛生士&口育士として伝えたいこと
体験+専門家の視点―親子でがんばる「きっかけ」づくり
三人の子育てで得た実感は「なかなか思う通りにはいかない」ということ。ただ、小さな成功を積み重ねることで「親子のお口ケア時間」が不思議でした。
○泣いてもいい。途中でやめる日があっても大丈夫。
○歌やごほうび、スキンシップで「やらされる感」を減らすことができる近道。
○自分の子と他の子、兄弟の間でも全く反応が違う。
○お口ケアは「歯を磨く」だけが目的じゃない。親子のコミュニケーションのきっかけ。
仕上げ磨きのトラブルが減り、「楽になった」と感じる家庭が増えることを願っています。
まとめ―「泣きの磨き仕上げ」は成長の証、焦らず付き合っていきましょう
・仕上げ磨きのギャン泣きは親子ともつらい時期。 しかし一時的なものであり、親の責任でも、子どものワガママでもありません
・泣いた日も逃げ回った日も、そしてうまく磨けた日もすべて「親子の成長の記録」。うまくいかないエピソードを大切にすることで、次のステップに必ず役立ちます。「毎日違っていい」、これが我が家流の仕上げ磨きです。
親子で「楽しく続く」お口ケアの一助となれば幸いです。


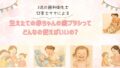
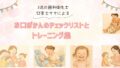
コメント