はじめに
こんにちは。歯科衛生士・口育士として、日々多くの方と「食べること」「飲み込むこと」に向き合っています。年齢や体調の変化、病気などで「飲み込みにくさ」を感じる方が増えていますが、「何を食べたらいいの?」「危ない食材は?」と悩む声もよく聞きます。
私自身、訪問歯科の経験や患者さんのサポートを通じて、食材選びや調理の工夫の大切さ、そして「食べる楽しみ」を守ることの重要性を痛感してきました。
この記事では、飲み込みやすい食材・危ない食材の見分け方と、実際に役立つ工夫、そして私自身や現場での体験談をたっぷり交えながらお伝えします。
飲み込みやすい食材とは?その特徴と選び方
飲み込みやすい食材の3つの条件
飲み込みやすい食材には共通する特徴があります。
-
適度に変形し、やわらかいこと
-
口の中でまとまりやすく、バラバラにならないこと
-
喉をすべるように通り、ベタつかないこと
この3つを満たすことで、誤嚥や窒息のリスクを減らし、安心して食事を楽しめます。
具体的なおすすめ食材
-
豆腐・はんぺん・温泉卵・ヨーグルト・バナナ・アボカド・とろろ(山芋)・モロヘイヤ・絹ごし豆腐・サバの水煮・ひきわり納豆・ポタージュスープ・プリン・ティラミスなど。
-
じゃがいもや里芋などの芋類は加熱でやわらかくなりやすく、牛乳やスープで伸ばすとさらに飲み込みやすくなります。
食材のつなぎ・とろみの工夫
-
マヨネーズやとろけるチーズを加えると、野菜や卵がまとまりやすくなり、飲み込みやすくなります。
-
とろみ調整食品を使い、飲み物や汁物に適度なとろみをつけるのも有効です。
体験談:食事介助から学んだこと
嚥下障害がある患者さんでした。最初はお粥や豆腐、ヨーグルトなどを中心にしていましたが、どうしても「味気ない」と感じていたようです。
そこで、温泉卵にとろみをつけた出汁をかけたり、里芋を牛乳でのばしてマッシュ状にしたり、プリンやバナナも活用することで「美味しい」「食べやすい」と笑顔が増えました。
飲み込みにくい・危ない食材の特徴と注意点
飲み込みにくい食材の4つのパターン
-
パサパサ系:ゆで卵の黄身、焼き魚、クッキー、せんべいなど。
-
パラパラ系:そぼろ、ちりめんじゃこ、みじん切り野菜など。
-
ベタベタ系:餅、団子、求肥、焼きのり、わかめなど。
-
サラサラ系:水、お茶、ジュースなどの透明な液体。
特に注意が必要な食材
-
餅や団子:粘り気が強く、喉に張り付きやすい。
-
パンやクッキー:水分が少なく、口の中でパサついてまとまりにくい。
-
海苔やわかめ:喉に貼りつきやすく、窒息のリスク。
-
根菜の繊維(ごぼう、れんこん、えのき等):繊維が多く、引っかかりやすい。
-
弾力が強いもの(イカ、タコ、こんにゃく等):噛み切りづらく、飲み込みにくい。
-
魚の骨や皮:誤嚥や窒息の原因になるため、必ず取り除く。
体験談:患者さんとの現場エピソード
ある高齢の患者さんが「おにぎりが好き」とおっしゃっていたので、最初は普通のご飯で作っていました。しかし、パラパラと口の中でバラけてしまい、むせることが多発。
そこで、少し粘り気のあるご飯にし、具材も刻んで混ぜ込み、ラップでしっかり握って小さめにすることで、むせることなく「美味しい」と完食されました。
飲み込みやすくするための調理・食事の工夫
とろみの使い分け
-
薄いとろみ:スプーンを傾けると流れ落ちる程度。ストローで吸える。
-
中間のとろみ:スプーンでとろとろと流れる。ストローはやや吸いづらい。
-
濃いとろみ:スプーンを傾けても形が保たれる。ストロー不可。
むせや飲み込みの様子を見ながら調整していきましょう。
調理のポイント
-
食材は「やわらかく」かつ「まとまりやすく」
例:野菜は短めに切り、電子レンジや煮込みでやわらかく。 -
水分を加えてのばす
例:いも類は牛乳やスープでマッシュに、卵はマヨネーズで和える。 -
つなぎ食材を活用
例:豆腐やアボカド、里芋などをハンバーグや和え物に加えると、まとまりやすくなります。 -
骨や皮、筋は必ず除去
魚や肉は下処理を徹底し、細かくたたいてやわらかくする。
年齢や状態別・飲み込みやすい食事の工夫
乳幼児・子ども
-
よく噛む習慣をつけることが大切。あまり噛まずに飲み込める食事ばかりだと、顎の発達や歯並びに影響が出ることも。
-
おやつには、りんごや焼き芋、煮豆など噛むトレーニングになるものを。
体験談:親子での「カミカミ大会」
我が家では週末色々な食材の野菜をスティック状・生・ゆでたりと食感などを変えてよく噛む昼食にして家族で「カミカミ大会」をしていました。セロリなどはシャキシャキしてるー!きゅうりはカリカリして硬い!など楽しみながら噛んで口の機能を発達させていきました。子ども達は週末になると今度はどんな野菜使うの?など徐々に好き嫌いもなくなってきていました。

高齢者・嚥下障害のある方
祖父は食事中よくむせていました。何がむせているのか、家族で様子を見ていたら、液体がむせるようでした。お味噌汁やお茶でむせていました。そこで液体に片栗粉やとろみ材を使いとろみをつけることで、むせが減ってきました。
また冷たい飲み物や熱いスープなどもむせやすくなるので、飲みやすい温度の飲み物を用意しましょう。
体験談:訪問歯科での工夫
訪問歯科の現場では、患者さんの嚥下機能や口腔内の状態に合わせて、管理栄養士や言語聴覚士と連携しながら食事内容を提案しています。
例えば、舌でつぶせる柔らかさの煮魚や、豆腐ハンバーグ、ポタージュスープなどが好評です。ご家族には「食べる楽しみ」を残すために、見た目や味付けにも気を配るようアドバイスしています。
食べる力を守るために大切なこと
口腔ケアと食事の関係
-
口腔内の清潔を保つことで、嚥下機能や味覚も守られます。歯科衛生士として、定期的な口腔ケアやリハビリの大切さを強調しています。
-
「食べること」は生きる力そのもの。介護や病気の現場で「食べたいけど食べられない」方と向き合うたび、日々のケアや工夫の重要性を実感します。
- 「食べたい!!」と思う気持ちに寄り添えるように、味・素材・形態・食具工夫しながら最期までお口からお食事がとれる環境を整えてあげたいですね。

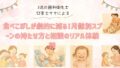
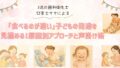
コメント