虫歯との闘いが教えてくれた真実
乳児検診で宣告されたショック
毎日欠かさず仕上げ磨きをしていたのに…。末っ子の娘は1歳半健診の歯科検診で虫歯の疑いがあると言われてしまいました。歯科衛生士から「おやつの与え方に問題がありますね」と指導を受け、私は愕然としました。
今でもあのショックは忘れられません。幸い歯科医院で詳しく診てもらったところ、虫歯ではなく、歯の溝が深くなっているだけで、虫歯ではないが虫歯にはなりやすいです、とのことでした。
それから20年、3人の子ども達の虫歯ゼロを通して確立したノウハウを余すところなくお伝えします。
おやつは敵ではない
「おやつ=悪」という考え方は今でも根強く残っています。栄養士のアドバイスと歯科医師の指導を融合させ、栄養補給と虫歯予防を両立させる方法を編み出したのです。鍵は「選択」と「リズム」にありました。
長男は身体も大きく食べるのが大好きでした。3食のごはんでは途中でお腹がすいてしまい、午前中と午後に1回ずつ間食を摂っていました。それは甘いお菓子などではなく、おにぎりやサンドウィッチなど腹持ちの良い軽食のようなおやつにしていました。すると機嫌よく1日を過ごすことができ、1日元気に動き回っていました。2歳健診では保健師さんに体重・身長ともによく成長しています、言われました。
また歯科健診でも虫歯もなく、あごもバランスよく成長しているよ、との健診結果でした。
間食というと、甘いおやつのイメージですが、決してお菓子でなくてもいいということを長男の時に感じました。以降次男も末っ子長女も甘いお菓子を手放せないということはありませんでした。
革命的なおやつ選び5原則
自然の甘みを最大限活用
我が家の定番は干し芋とバナナチップス。砂糖不使用ながら自然な甘みが特徴で、次男が3歳の時に「ママの手作りおやつが1番!」と言ってくれたのが忘れられません。市販品なら無添加のドライフルーツがおすすめです。
歯に貼り付かない形状選び
ある日、次男がおやつを噛み切れずにのどにつまりそうになった求肥餅の苦い経験があります。粘着性食品の危険性を痛感。現在は海苔巻きせんべいや野菜チップスを常備し、歯の溝に詰まりにくい形状を重視しています。
カルシウム補給を兼ねる
チーズや乳製品はカルシウムが豊富に含まれます。
我が家ではカットチーズを冷凍庫に常備し、夏場は天然のアイス代わりに。カルシウムが歯を強化し、噛む動作が唾液分泌を促すダブル効果があります。子ども達は今でもチーズが大好きです!
タイミング管理の極意
14時30分の魔法
我が家のおやつタイムは厳格に14時30分。この時間設定には科学的根拠があり、食後2時間経過で空腹になりやすく、夕食までの時間を確保できるため。夕食はお腹を減らして食べるようにしていました。
初めは「おやつをまだ食べたい!」と泣いていた次男も、1ヶ月で体内時計が調整されました。しっかり量を食べればまた午後も機嫌よく過ごせました。
20分ルールの徹底
歯科医師から教わった「20分以内完食ルール」。唾液の働きで20分後に唾液の虫歯予防効果が高くなる性質があるそうです。砂時計を使ったゲーム感覚の取り組みが功を奏し、子どもたちは自然と早食い防止にも。食べ終わった後の「うがいタイム」を楽しい習慣に変える工夫が鍵でした。
失敗から学んだ危機管理術
祖父母対策マニュアル
義父母の「愛のお菓子攻撃」にどう対処するか。我が家で作成した「おじいちゃん・おばあちゃんへのお願いリスト」が効果的でした。キシリトールグミやノンシュガーゼリーを常備してもらうなどの対策で、トラブルを8割削減。祖父母もどんなものが喜ばれるか具体的に言ってもらってよかったと言われました。どうせ買ってくれるなら喜んでもらえるおやつがいいですもんね!
外出先の緊急対応
遠足で配られたキャラメルを機に開発した「緊急うがいキット」。キャラメルは歯にくっつきやすく、甘さも強いため虫歯のリスクがとても高いですが、水筒にハーブティー(殺菌作用あり)を入れ、口をゆすぐ方法を考えました。これなら外で歯みがきができないときでも手軽にケアできます。
よくある疑問Q&A
Q. どうしてもチョコレートを欲しがる時は?
A. 高カカオチョコを選び、食後すぐに緑茶を飲む習慣を。カテキンの殺菌作用とフッ素の相乗効果でリスク低減。我が家では月1回の「チョコデー」を設け、特別感を演出しています。
我が家の次男はチョコレートが大好きな時期がありました。スーパーに行くとチョコレートを買ってと持ってきました。そんな時は、高カカオの甘さの少ないチョコレートや好き嫌いの野菜が食べられたら買ってあげるなどと条件つきで買ってあげたりしていました。
Q. 兄弟でおやつを分け合う場合の注意点は?
A. 個包装のおやつを年齢に応じて分配。長男にはナッツ、次男には小魚、末っ子には野菜スティックなど、発達段階に合わせたおやつをあげている時期がありました。兄弟で同じ量では下の子には多すぎたり、食べるのが難しい年齢の食材もあります。
トレーに分けて「自分用」を意識させて、自分専用という特別感を持たせてあげると子ども達も満足そうに分けられたおやつを食べていました。
未来の笑顔を守るために
20年間の試行錯誤でたどり着いた結論は「制限ではなく選択」です。完全排除ではなく賢い選択を続けた結果、3人とも永久歯に生え変わった今も虫歯ゼロを達成しました。毎日のおやつタイムが、家族の健康を育む大切な時間になりました。
甘いお菓子は常習性があります。次男は長男が食べていたチョコレートを一口食べてから、しばらくチョコレートじゃなきゃ嫌だという時期がありました。甘いものの常習性の怖さを実感して、工夫して絶対に常習性から離脱させなきゃいけないなあと強く感じました。
今日から始める小さな変化が、5年後の子どもの虫歯ゼロを目指して頑張りましょう!
家族で、祖父母とみんなで協力すること、情報を共有することが子どもの歯を育てます!

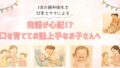
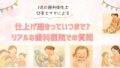
コメント