はじめに
こんにちは。歯科衛生士・口育士として、日々多くの親御さんから「おしゃぶりや指しゃぶり、どうしたらやめさせられるの?」「歯並びへの影響は?」といったご相談を受けます。
私自身も3児の母として、我が子の指しゃぶりやおしゃぶりとの付き合い方に悩んだ経験があります。
本記事では、専門家としての知識と、リアルな親子の体験談を交えながら、無理なく、子どもが自信を持って卒業できる方法を詳しくお伝えします。
おしゃぶり・指しゃぶりはなぜ起こる?その役割と心理
生理的な行動としての意味
おしゃぶりや指しゃぶりは、赤ちゃんにとってごく自然な行動です。
生後1~2ヶ月頃から始まり、口に刺激を与えることで安心感を得たり、手と口の協調運動を促進したりする役割があります。
実際、赤ちゃんはお腹の中にいる時から指しゃぶりをしています。
気持ちを落ち着かせる「セルフコントロール」
言葉で気持ちを伝えられない時期の子どもにとって、指しゃぶりやおしゃぶりは自分で気持ちを落ち着かせる大切な手段です。
眠い時や不安な時、退屈な時など、さまざまな場面で見られます。
いつまでに卒業すればいい?歯並びや健康への影響
2歳までは自然な行動
多くの専門家は、2歳までは無理にやめさせる必要はないとしています。
この時期はまだ生理的な行動であり、成長とともに自然に減っていくことが多いです。
3歳以降は注意が必要
ただし、3歳を過ぎても頻繁に指しゃぶりやおしゃぶりが続く場合、歯並びや噛み合わせへの影響が出てくる可能性があります。
-
上顎前突(出っ歯)
-
開咬(前歯が噛み合わず開いたままになる)
-
歯列の狭窄(歯並びが狭くなる)
-
口呼吸の習慣化
これらは将来的な歯科治療のリスクにもなりますので、2歳すぎたら卒業を意識しましょう。
卒業のタイミングと子どもに合わせた進め方
適切な卒業時期と判断基準
-
1歳半~2歳歳頃が理想的な卒業時期とされています。
-
幼稚園入園や新しい生活環境への移行など、子どもの成長や生活の変化に合わせてタイミングを選ぶとスムーズです。
子どものペースを大切に
無理にやめさせようとすると、逆にストレスや不安を強めてしまうこともあります。
子ども自身が「やめたい」と思えるきっかけ作りや、納得して手放せるような工夫が大切です。
体験談から学ぶ!おしゃぶり・指しゃぶり卒業法
子ども自身に選ばせる
体験談:おしゃぶりを自分で捨てた娘
「3歳の誕生日をきっかけに『お姉さんになったから、おしゃぶりは赤ちゃんにあげようか』と話しました。娘は最初は寂しそうでしたが、自分で納得しておしゃぶりを箱に入れてお別れ。数日は泣きましたが、その後はすっきりした様子で、朝までぐっすり眠れるようになりました。」(30代ママ)
物理的な工夫で無意識を防ぐ
体験談:指に絆創膏を貼って卒業
「寝るときやテレビを見ているとき、無意識に指しゃぶりをしてしまう娘。本人もやめたい気持ちはあったので、指にバンドエイドを貼ってみました。違和感があることで自分で気づき、数日で癖がなくなりました。」
絵本やご褒美作戦
体験談:絵本で楽しく指しゃぶり卒業
「『ゆびたこ』という絵本を読んであげたところ、指を口に持っていくたびに『ゆびたこおじさんになっちゃうよ!』と声をかけると、自然とやめることができました。怖がらせるより、楽しい雰囲気で進めたのが良かったと思います。」
体験談:ご褒美でモチベーションUP
「爪を噛まなかったらサーティワンに行こう!と約束したら、毎日『見て!伸びたよ』と嬉しそうに報告してくれました。ご褒美作戦、効果ありでした。」
代替行動を提案する
体験談:お気に入りのぬいぐるみで安心感をサポート
「寝るときだけ指しゃぶりをしていたので、ぬいぐるみを一緒に寝かせるようにしたら、指しゃぶりの回数が減りました。安心できる環境作りが大切だと実感しました。」
歯科衛生士・口育士の視点から:卒業をサポートするコツ
おしゃぶり選びにも工夫を
歯並びに配慮したおしゃぶり(根元が薄い、舌の動きを妨げない形状など)を選ぶことで、歯への影響を最小限にできます。
食事・運動・遊びで口の機能を育てる
-
食事時は姿勢を正し、前歯でかぶりつく習慣をつける
-
ハイハイや公園遊び、吹き戻しやラッパなど口や舌を使う遊びを取り入れる
-
口呼吸を防ぐために、唇を閉じる意識を持たせる
スキンシップや声かけで安心感を
指しゃぶりやおしゃぶりがなかなかやめられない場合は、スキンシップや会話を増やし、子どもの気持ちを安定させてあげましょう。
子どもが「自分でやめられた!」と感じる体験談
体験談:周囲の変化がきっかけに
「幼稚園に入って、周りの子が指しゃぶりをしていないことに気づいた娘。『恥ずかしい』という気持ちが芽生え、自分からやめることができました。」
体験談:第三者の声が効果的だった例
「歯医者さんに『もうお姉さんだからやめようね』と言われたことで、すんなり卒業できました。親が言うよりも、第三者の言葉が響くこともあるんですね。」
卒業までの流れと実践的ステップ
日中の使用・癖を減らす
まずは日中の指しゃぶりやおしゃぶりを控え、夜間だけにするなど段階的に減らしていきます。
子どもと一緒に目標を決める
「○歳になったらやめようね」「幼稚園に入る時にバイバイしよう」など、子どもと話し合って目標を共有しましょう。
卒業記念や代替品を用意する
卒業記念に新しいおもちゃやぬいぐるみを用意し、ポジティブな体験と結びつけるのも効果的です。
無理にやめさせるのは逆効果?親の心構え
「自然にやめる」を信じて見守る
多くの場合、成長とともに自然にやめていきます。
無理にやめさせようとせず、子どものペースを大切にしましょう。
どうしてもやめられない場合は専門家へ相談
4歳を過ぎてもやめられない、歯並びや指の皮膚に異常が見られる場合は、小児歯科や口育士・保健師などに相談してください。
まとめ:子どもの成長を見守りながら、親子で乗り越える卒業への道
おしゃぶりや指しゃぶりは、赤ちゃんの成長に欠かせない大切な行動です。
卒業のタイミングや方法は一人ひとり異なりますが、親子で一緒に考え、子ども自身が「やめられた!」と自信を持てる経験にしてあげることが何より大切です。
私自身も、子どものペースに寄り添いながら、時には失敗を繰り返し、たくさん悩みました。
でも、卒業できた時の子どもの笑顔は、何よりも大きな成長の証です。
ぜひ、この記事が悩める親御さんのヒントや励みになれば幸いです。
よくある質問(Q&A)
Q. 何歳までにやめさせればいいですか?
A. 2歳までは自然な行動。3歳を過ぎても続く場合は、歯並びへの影響を考え、卒業を意識しましょう。
Q. 無理にやめさせるとどうなりますか?
A. 無理にやめさせると、ストレスや不安を強めることがあります。子どものペースに合わせて進めましょう。
Q. どうしてもやめられない場合は?
A. 歯科衛生士や口育士、小児科医に相談してください。専門的なアドバイスが受けられます。
最後に
おしゃぶり・指しゃぶりは、子どもの心と体の発達に寄り添う大切な行動です。
卒業までの道のりは決して一筋縄ではいきませんが、親子で一緒に乗り越えることで、子ども自身の自信や自己肯定感にもつながります。
どんな小さな一歩でも、子どもの成長を温かく見守ってあげてください。
歯科衛生士・口育士として、これからも皆さんの子育てを応援しています。
(本記事は歯科衛生士・口育士の経験と、実際の親子の体験談、専門家の知見をもとに執筆しています)

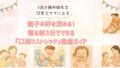
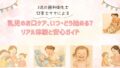
コメント