口腔機能発達不全症とは
口腔機能発達不全症の定義と背景
「口腔機能発達不全症」とは、食べる・話す・呼吸するなどの口の機能が十分に発達していない、または正常に機能できていない状態を指します。
これは、明らかな病気や障害がないにもかかわらず、口腔機能が年齢相応に獲得できていない場合に診断されます。主に15歳未満の子どもが対象で、特に幼児期〜学童期の発見が重要とされています。
この疾患は平成30年に正式な病名として認定され、近年その認知が広がりつつありますが、まだ一般の保護者や一部の歯科医療従事者の間でも十分に浸透していないのが現状です。
どんな症状が現れるの?
-
口をぽかんと開けている
-
食べ物をうまく噛めない・飲み込めない
-
食べこぼしが多い
-
発音が不明瞭、滑舌が悪い
-
口呼吸が多い
-
歯並びが悪い
-
指しゃぶりや唇を噛む癖がある
-
いびきをよくかく
-
姿勢が悪い
これらの症状は、日常生活の中で「ちょっと気になるな」と思う程度のことが多く、本人に自覚がない場合がほとんどです。そのため、家族や周囲の大人が早く気づいてあげることが大切です。
我が家の子ども達も「いびきをする・食べこぼしが多い」に該当しました。いびきは疲れているのかな、食べこぼしは上手に食べられない時期かなと思っているだけでした。この二つがまさか口の機能の問題だとは思いませんでした。歯医者さんに健診の時、口の機能の発達不全がみられます。いびきやたべこぼしなどありませんかと言われ、ハッとしました。
体験談
きっかけは保育園の先生の一言
我が家の長男が保育園の先生から「お子さん、いつもお口が開いていますね」と言われたことでした。最初は「癖かな?」くらいにしか思っていませんでしたが、食事の食べこぼしもあったのでもしかしてこれもお口が開いていることと関係しているのかもと思い歯科健診で相談しました。これが将来的な歯並びや発音、さらには全身の健康にも影響する可能性があると知り、歯科医院に受診した方もいらっしゃいました。
歯科医院での検査とアドバイス
歯科医院では、噛み合わせや舌の動き、口を閉じる力などをチェックします。「口腔機能発達不全症の傾向がある」と診断。
歯医者さんに「早いうちに気づいて良かったですね。トレーニングや生活習慣の見直しで、十分改善できますよ」と説明をうけ、歯科衛生士で口育士である私のトレーニングを受ける流れになります。
家庭での取り組み
先生のアドバイスをもとに、次のようなことを実践しました。
-
食事中はよく噛むことを意識
-
姿勢を正すために椅子の高さを調整
-
お風呂でぶくぶくうがいの練習
-
指しゃぶりをやめるための工夫(手遊びや絵本など)
数ヶ月続けるうちに、少しずつ口を閉じていられる時間が増え、発音もはっきりしてきました。何より、子ども自身が「できた!」と喜ぶ姿が増えたのが一番の変化でした。
早期発見のためのチェックリスト
家庭でできる簡単チェック
お子さんに次のような様子が見られたら、口腔機能発達不全症の可能性があります。気になる項目があれば、歯科医院で相談してみましょう。
-
いつも口が開いている
-
歯並びが悪い
-
食べるのが極端に早い・遅い
-
食べ物を丸飲みする・食べこぼしが多い
-
鼻呼吸ではなく口呼吸が多い
-
いびきをよくかく
-
発音がはっきりしない、言葉の発達が遅い
-
舌が短くて、舌を突き出すと先端がくぼむ
-
指しゃぶりや唇を噛む癖がある
-
姿勢が悪い、背中が丸まっている
-
むし歯が多い
歯科医院での検査内容
歯科医院では、保護者からの聞き取りに加え、以下のような検査が行われます。
-
噛み合わせや歯並びのチェック
-
口唇を閉じる力や舌の力の測定
-
舌や唇の動き、発音の確認
-
口呼吸やいびきの有無
-
生活習慣や食事内容の確認
口腔機能発達不全症の原因とリスク
なぜ起こるのか?
口腔機能発達不全症は、遺伝的な要素だけでなく、生活習慣や環境要因も大きく関わっています。
例えば、柔らかい食べ物ばかり食べていると噛む力が育たなかったり、スマホやゲームで猫背の姿勢が続くと口周りの筋肉が弱くなったりします。
また、指しゃぶりや口呼吸、舌の癖なども、口腔機能の発達に悪影響を及ぼします。通院してくるお子さんも、寝る前の指しゃぶりがなかなかやめられず、歯並びや発音に影響が出はじめています。
放置するとどうなる?
-
不正咬合(歯並びの悪化)
-
発音障害
-
食べ物をうまく噛めない・飲み込めない
-
虫歯や歯周病のリスク増加
-
睡眠時無呼吸症候群のリスク
-
将来的な全身の健康リスク
特に、成長期に適切な介入がなされないと、大人になってからも口腔機能の低下が進みやすくなります。健康な人生を送るためにも、子どものうちからのケアが重要です。
口腔機能発達不全症の改善方法
歯科医院でのサポート
歯科医院では、生活指導やトレーニングメニュー、必要に応じて矯正治療などを行います。ガムトレーニングや「あいうべ体操」、トレーニング器具など、子どもが楽しみながら続けられる方法があります。
また身体の育ちも大切です。筋力が口の機能を成長させます。外遊びをたくさんして、たくさん笑ってお口を使っていきましょう!
家庭でできるトレーニング
-
よく噛む食事を心がける(おにぎり、野菜スティックなど)
-
姿勢を正して食事をする
-
お風呂でぶくぶくうがい
-
吹き戻しや風船遊びで口の筋肉を鍛える
-
「あいうべ体操」や顔じゃんけん
私の子ども達3人は、ガムトレーニングが大好きで、毎日20分ほどテレビを見ながらガムを噛む習慣ができました。最初は片方でしか噛めなかったのが、数ヶ月で左右バランス良く噛めるようになり、唇の筋力検査の再検査にも「数値が上がっているね!」と褒めてもらえました。
保護者のサポートがカギ
子どもは「楽しい」「できた!」という成功体験が大好きです。無理にやらせるのではなく、遊びや日常生活の中で自然に取り入れることが、継続のポイントです。私自身も、子どもと一緒に「あいうべ体操」をしたり、食事の時間を楽しむ工夫をすることで、親子のコミュニケーションも深まりました。
まとめ:早期発見・早期対応で子どもの未来を守ろう
口腔機能発達不全症は、決して珍しいものではありません。むしろ、現代の生活環境では誰にでも起こりうる身近な問題です。しかし、早く気づいて適切に対応すれば、必ず改善が期待できます。
私自身の体験からも、「ちょっとした気づき」が子どもの将来を大きく左右することを実感しました。ぜひ、今回ご紹介したチェックリストを活用し、お子さんの口の健康を守る第一歩を踏み出してください。
もし気になる症状があれば、迷わず歯科医院に相談しましょう。専門家のサポートと家庭での取り組みで、子どもの健やかな成長を一緒に見守っていきましょう。
※本記事は、実際の体験談と専門家の知見をもとに執筆しています。お子さんの症状や状況によって対応が異なる場合がありますので、必ず専門の歯科医師に相談してみてくださいね。
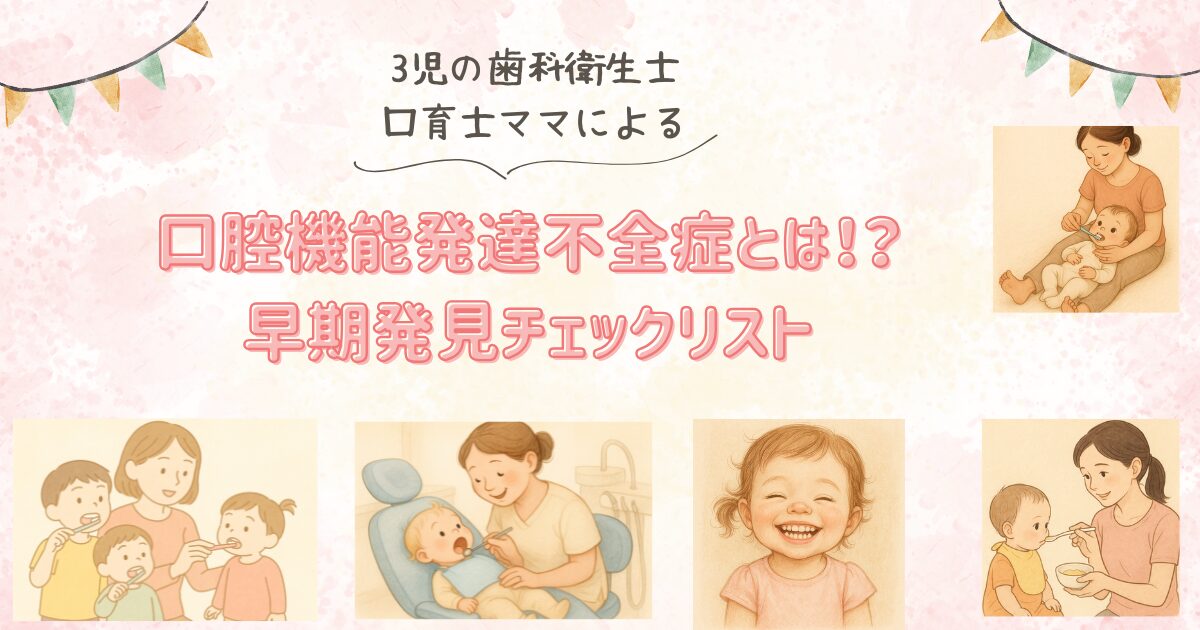
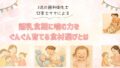
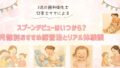
コメント