「子どもの口腔発達」と聞くと、虫歯予防や歯並びのことだけを思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、近年の研究や医療現場では、お口の発達が全身の健康や将来の生活の質にまで大きく影響することが明らかになっています。
私は歯科衛生士・口育士として多くの親子さんと関わり、私自身3児の母としても子どもの成長を見守ってきました。この記事では、最新の研究や歯科医院に相談に来院する歯科現場での実感、さらに私自身や親子の体験談を交えながら、子どもの「食べる力」と全身の健康の密接な関係について、わかりやすく解説します。
口腔機能発達不全症とは?現代の子どもに増えている理由
口腔機能発達不全症の定義と現状
私が歯科医院で働く中で特に印象に残っているのは、息子が離乳食を食べ始めたころのことです。食べ物を口に入れてもなかなか飲み込めず、やわらかいものばかり欲しがる様子に最初は戸惑いました。歯科健診で『口腔機能発達不全症の傾向がある』と指摘され、家族でトレーニングを始めたことで。今ではしっかり噛んで食べられるようになり、朝の目覚めもよくなったと感じています。
どんなサインがある?
-
食べるのが遅い、または早食い
-
やわらかいものばかり好む
-
よく噛まずに丸飲みする
-
口がぽかんと開いている
-
いびきをかく
-
滑舌が悪い
-
片側だけで噛む
-
口呼吸が多い
離乳食の時期に「食べ物をなかなか飲み込まない」「やわらかいものばかり欲しがる」などのサインが見られ、単なる個性かと感じる親御さんも多いと思います。しかし、歯科健診で「口腔機能発達不全症の傾向がある」と指摘され、生活習慣の見直しやトレーニングを始めるきっかけになりましたと来院するお子さんも増えました。
口腔発達と全身の健康がつながる理由
よく噛むことが脳と体を育てる
よく噛んで食べることで、口の筋肉や顎の発達だけでなく、脳神経の活性化や唾液分泌の増加、肥満防止、虫歯や歯肉炎の予防にもつながります。
三人の子どもたちの離乳食期を振り返ると、「よく噛む」ことを意識して食材を工夫した子は、集中力や食事のリズムも良く、体調を崩しにくいと感じました。
姿勢や全身運動と口腔発達の関係
口腔機能は全身の運動機能と深く結びついています。
例えば、正しい姿勢で座れない子は、舌や顎の動きが不十分になりやすく、丸飲みや食べこぼしが増えます。
ある相談のお子さんでは椅子に座るのが苦手で、食事中にすぐ立ち上がってしまうタイプでした。体幹トレーニングや遊びを取り入れ、座位が安定してくると、噛む力や飲み込む力も目に見えて成長しました。
これは舌の筋肉は全身運動で養われるからです。
口腔機能の遅れが将来に与える影響
口腔機能発達不全症を放置すると、歯並びや噛み合わせの問題、顔のゆがみ、呼吸障害、学習や運動パフォーマンスの低下、さらには成人後の健康リスクまで高まることがわかっています。
実際、私が支援した小学生のケースでも、口呼吸や噛み合わせの問題が集中力や運動能力の低下、睡眠障害につながっている例がありました。
最新研究でわかった!子どもの食習慣と口腔発達の相互作用
幼児期の食習慣が学齢期に影響
幼児期の食習慣が、学齢期の噛む・飲み込むといった口腔機能に大きな影響を与えることが、最新の研究で明らかになっています。
離乳食の時期に「よく噛む」「いろいろな食感を経験する」「自分で食べる練習をする」などの経験が、将来の口腔機能の発達に直結します。
ヒトは、苦みは毒・酸っぱさは腐敗という機能をもっています。それを色々な味覚を味わうことで、脳が統合され、成熟し味覚が育っていきます。
子供の頃食べられなかった山菜の苦みや酢の物なども大人になると美味しく感じるという経験をした方もいると思います。
相談例:食習慣改革
離乳食期は、つい食べやすいペースト状のものばかり与えがちです。その結果、2歳ごろまで「丸飲み」や「食べこぼし」が多く、歯科健診でも指摘されました。
後期以降から少しずつ固さや大きさを変え、手づかみ食べやスプーン練習も積極的に取り入れたところ、噛む力や食べる意欲がぐんと伸びました。
いつでも練習すれば食べれるようになります。

生活習慣・遊び・姿勢の大切さ
スマホやゲーム機の普及で、口を使った遊びや会話が減り、姿勢が悪くなっている子どもが増えています。
全身を使った遊びや正しい姿勢を意識することが、口腔機能の発達にも直結します。
相談例:家族で取り組む「お口遊び」
我が家では、毎晩の歯みがきタイムを家族のイベントにしています。子ども達は『誰が一番きれいに磨けるか』と張り切って歯ブラシを持ち、パパは『奥歯までしっかり磨けたよ!』と声をかけます。
休日には『早口言葉大会』や『風船ふくらまし大会』も開催し、子ども達は最初は苦戦していましたが、繰り返すうちに舌や口の動きが滑らかになり、発音もはっきりしてきました。
口腔発達が全身の健康に与える影響
呼吸・睡眠・集中力への影響
口呼吸やいびきは、口腔機能発達不全症のサインであり、睡眠障害や集中力低下、学習・運動パフォーマンスの低下にもつながります。
ある患者さんはいびきの悩みでご相談をうけました。歯科での指導と生活習慣の見直しで、いびきが減り、朝の目覚めも良くなりました。とお声をいただきました。一つの原因ではありませんが、お口の筋肉不足も考えてみてください。
免疫力・感染症リスク
口腔ケアを徹底することで、口腔内の細菌を減らし、免疫力が高まり、感染症リスクも低減します。
また口を閉じ、鼻呼吸と唾液で潤った口は、風邪をひきにくいというデータもでています。
私自身、子どもたちの歯みがき習慣を徹底したことで、風邪やインフルエンザにかかる頻度が減ったと実感しています。
歯並び・顎・顔面の成長
正しい噛み方や舌の動きは、顎や顔面のバランスの良い成長に不可欠です。
離乳食期から「舌を上にあげる」「左右バランスよく噛む」ことを意識すると、歯並びや顎の発達も順調に成長します。
口腔機能発達不全症を防ぐための家庭でできる工夫
噛む力を育てる食事の工夫
-
食材の固さや大きさを段階的に変える
-
よく噛む必要がある食材(野菜スティック、かためのおにぎりなど)を積極的に
-
手づかみ食べやスプーン練習を取り入れる
姿勢と遊びの工夫
我が家では、食事の際に子どもの足が床につくように踏み台を用意しています。長女は最初、すぐに立ち上がって遊びたがるタイプでしたが、踏み台を使うことで姿勢が安定し、食事に集中できるようになりました。
また、公園で体を思いっきり動かしたり、家ではストローを吸いあげたり、大きな風船を膨らませたりして、口や体の動きを鍛える遊びを積極的に取り入れます。
家族みんなで口腔ケア
-
毎日の歯みがきを家族で習慣化
-
定期的な歯科健診・フッ素塗布
-
食後に水やお茶でお口を洗い流す
体験談:家族の協力がカギ
三人の子育てを通じて感じたのは、「家族みんなで取り組むこと」の大切さです。
兄弟で歯みがきタイムを競争したり、パパも一緒に「お口遊び」に参加したりすることで、子どもたちのやる気や継続力がアップしました。
食習慣の見直し
次男が離乳食を始めた頃、つい食べやすいペーストばかり与えていました。すると2歳ごろまで『丸飲み』や『食べこぼし』が多く、歯科健診でも指摘されました。そこで後期以降から少しずつ固さや大きさを変え、手づかみ食べやスプーン練習も積極的に取り入れたところ、噛む力や食べる意欲がぐんと伸びました。
今ではいろいろな食感を楽しみながら自分で食べられるようになり、食事の時間が家族の楽しいコミュニケーションの場になっています。
専門家としてのアドバイスと体験
歯科衛生士として働く中で、多くの親御さんから『うちの子、口がぽかんとあいている』『いびきをかく』などの相談を受けます。
私自身も三児の母として、子どもの口の動きや姿勢に気を配り、専門家のアドバイスを積極的に取り入れてきました。例えば体幹トレーニングや口の筋肉を鍛える遊びを取り入れることで、子ども達の『食べる力』や『話す力』が大きく成長したと実感しています。
学童期への影響
長女が小学校に入ってからも、幼児期に身につけた『よく噛む』『自分で食べる』食習慣が生きていると感じています。給食の時間にしっかり噛んで食べている様子や、友達と楽しく会話しながら食事を楽しむ姿を見て、幼い頃からの積み重ねが学童期にも大きな影響を与えていると実感しています。
また歯科健診でも『口腔機能がしっかり発達している』と評価され、親としても安心しています。
まとめ・応援メッセージ
三児の成長を見守る中で、毎日の小さな積み重ねが子ども達の『食べる力』や『話す力』を育て、心や体の健康、そして自身や自己肯定感にもつながっていると強く信じています。専門家としても母親としても、『食べる力』は子どもたちの未来を支える大切な土台だと確信しています。
お子さんの『食べ方』『噛み方』『歯並び』『お口ぽかん』など、気になることがあれば、ぜひ早めに歯科医院や専門家に相談してみてください。
家族みんなで楽しく取り組むことで子ども達の健やかな成長を応援します!

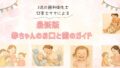
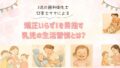
コメント