「子どもの歯並びは遺伝だから仕方ない」と思っていませんか?実は、乳歯期からの生活習慣や食事、毎日のちょっとした工夫で、将来の歯並びや顎の発達は大きく変わります。
私は歯科衛生士・口育士として多くの親子をサポートし、三児の母としても家庭で実践してきました。
この記事では、矯正治療が必要になるリスクを減らすために、乳歯期からできる具体的な生活習慣改革と、私自身の体験談を交えてご紹介します。
乳歯期の歯並び、なぜ気にするの?
「乳歯だから多少ガタガタでも大丈夫」と思っていた私ですが、次男の前歯が重なって生えてきたときは、正直かなり動揺しました。夜な夜なネットで情報を調べたり、歯科衛生士の先輩に相談したり・・・。その中で「乳歯のすき間は、実は成長の証拠。焦らず、今できる習慣を見直してみて」と言われたことが、私の意識を大きく変えました。
この経験から「乳歯の歯並びこそ、将来の歯並びの土台になる」と実感しました。実際、生活習慣を少しずつ変えていくことで、子どもの歯並びや表情が明るくなっていく様子を目の当たりにしました。
歯並びを悪くする主な原因
我が家の三兄弟を見ていて驚いたのは、同じ家庭でも「歯並びに影響する癖や習慣」が全く違うこと。
長男は指しゃぶりがなかなかやめらず、寝る前になると必ず指を口に入れていました。次男はテレビを見ながらの「ながら食べ」が癖になり、食事中の姿勢が崩れがち。末っ子はなぜか左側ばかりで噛むクセがついてしまい、ほっぺが片方だけふっくら・・・。
このように、指しゃぶりや口呼吸、片側噛み、姿勢の悪さなどは、どの家庭でも「うちの子だけ?」と悩みがちですが、実はよくあること。小さな癖が歯並びや顎の成長に影響することを、子どもたちの日々の変化から実感しています。
よく噛む食事で顎を育てる
長男の離乳食時代、最初は「食べやすさ重視」で柔らかいお粥やうどんばかりを与えていました。でも、2歳を過ぎてもなかなか噛む力がつかず、食事のたびに丸飲み・・・。
そこで、思い切って大きめの野菜スティックや、玄米のおにぎり、噛みごたえのある煮干しなどをおやつに用意。最初は嫌がっていましたが、手づかみ食べや「かぶりつきメニュー」を増やすうちに、顎のラインがしっかりしてきて、歯科健診でも「噛む力がついてきていますね」と褒められるように。
「噛む回数が増えると、食事時間も楽しくなる」ーーーこれは実際に子ども達と過ごして気づいた大きな発見です。
体験談:噛む工夫で変わった三兄弟
長男は、あまり噛まずに食べていました。そこで、野菜スティックやおにぎりを大きめに握り、しっかり噛ませるようにしたところ、食事時間が長くなり、自然と噛む回数も増えました。
次男は、噛みごたえのあるおやつ(りんごや煮干し)を取り入れることで、顎の発達が促され、歯科健診でも「顎がしっかりしていますね」と褒められました。
姿勢と食事環境を整える
三男は、食事中にすぐに立ち上がってしまい、落ち着いて食べられないのが悩みでした。よく観察してみると、椅子に立ったときに足が床につかず、ぶらぶらしているのが原因だと気づきました。
そこで、子ども用の足台を手作りして高さを調整。足がしっかりつくようになると、自然と座位が安定し、噛む力や飲み込みもスムーズに!
「姿勢が整うと、食事の集中力もアップする」ーーー家族で向き合って食べる時間が増え、ちょっとした会話も楽しめるようになりました。

口呼吸から鼻呼吸へ
次男はアレルギー性鼻炎があり、しょっちゅう口呼吸になっていました。最初は「仕方ない」と思っていましたが、口元が緩み、前歯が少し出てきたのを見てハッっとしました。そこで、毎朝「鼻うがい」と「お口閉じ体操」を親子で習慣化。鼻が詰まっているときは耳鼻科で相談し、薬を使ってでも鼻呼吸を確保。
「お口ぽかん」を見つけたら、「一緒にお口チャック!」とゲーム感覚で声かけ。少しずつですが、口元が引き締まり、歯並びも安定してきました。
体験談:鼻呼吸トレーニングの工夫
次男はアレルギー性鼻炎で口呼吸が多かったため、鼻うがいや鼻呼吸体操を毎日取り入れました。
指しゃぶり・おしゃぶり・頬杖の卒業
長男は2歳を過ぎても指しゃぶりがやめられず、私も「このままで大丈夫?」と不安でいっぱいでした。
無理にやめさせようとすると逆効果だったので、寝る前の絵本タイムや手遊びを増やしたり、「お兄ちゃんになったね」と成長を褒めたり。時には「今日は指しゃぶりゼロだったね!」とカレンダーにシールを貼って、一緒に達成感を味わいました。
卒業までの道のりは長かったですが、本人のペースを尊重したことで、自然と指しゃぶりが減り、歯並びも安定。親子の信頼関係も深まった気がします。
定期的な歯科健診とプロのサポート
乳歯期から歯科医院で定期検診を受けることで、歯並びや噛み合わせの異変を早期に発見できます。
我が家も3か月ごとに家族全員で歯科健診を受け、口腔トレーニングや歯科受診に慣れるようにしてきました。
歯並びによい食材・メニュー/注意したい食べ物や習慣
「おやつ=甘いお菓子」と思い込んでいた私ですが、口育の勉強を始めてから、りんごやさつまいも、手作りおにぎりなど「噛むおやつ」を意識して用意するように。
子ども達は最初「えー、お菓子がいい!」と抵抗していましたが、一緒にリンゴを切ったり、おにぎりを握ったりするうちに、「今日のおやつは何かな?」と楽しみにしてくれるようになりました。
噛む回数が増えたことで、顎の成長だけでなく、食事のメリハリや虫歯予防にもつながりました。
まとめ
三人の子ども達と向き合う中で、「完璧な歯並びを目指す」ことよりも、「毎日できる小さな工夫や声かけ」が将来の歯並びや健康に大きな違いを生むことを実感しました。
失敗もたくさんありましたが、家族みんなで楽しみながら続けることで、子どもたちの笑顔や自信にもつながっています。
「今日からできる一歩」を大切に、ぜひご家庭でも気軽に取り組んでみてください。

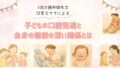
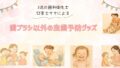
コメント