- はじめに
- 食べるのが遅い…その背景には何がある?
- 主な原因とその特徴
- 口腔機能の未発達・噛み合わせの問題
- 食事に集中できない環境
- 心理的な要因・プレッシャー
- 発達特性や個性
- お腹が空いていない・食事量が多い
- 箸やスプーンがうまく使えない
- 体調や気分の変化
- 私の現場体験談:食べるのが遅い子どもたち
- ケース1:咀嚼回数が多すぎて1時間以上かかる小学生
- 【対応】
- ケース2:おしゃべり好きな女の子の給食対策
- 【対応】
- ケース3:食事への執着が薄い子への工夫
- 【対応】
- 原因別アプローチと家庭でできる具体策
- 口腔機能・噛み合わせの未発達への対策
- 食事環境の見直し
- 心理的な負担を減らす声かけ術
- 発達特性や個性に合わせた工夫
- 「食べない状態が続いたら片付けてOK」ルール
- 食べるのが遅い子どもの“いいところ”も見つけよう
- よく噛む・味わう・マナーが良い
- 焦らず見守ることの大切さ
- まとめ:子どもの「食べるのが遅い」に寄り添うために
はじめに
「うちの子、どうしてこんなに食べるのが遅いの?」
「給食の時間が終わってもまだ食べている…」
日々の食卓や保育・学校現場で、こうした悩みを抱える保護者や先生は少なくありません。
歯科衛生士・口育士として、私自身も多くのご家庭から同じような相談を受けてきました。
また私自身も3人の子育てをする中で、同じように食べ始めてもいつまでも食べている子はどう違うんだろうと悩んだこともありました。
食べるのが遅い子どもには、実はさまざまな背景や個性が隠れています。
本記事では、実際の体験談や現場での工夫を交えながら、「食べるのが遅い」原因を多角的に分析し、今日からできる具体的なアプローチや声かけ術を徹底解説します。
食べるのが遅い…その背景には何がある?
主な原因とその特徴
口腔機能の未発達・噛み合わせの問題
我が家の末っ子の娘が小学校低学年の時に、給食でいつまでも食べているのでご家庭で様子を見てくださいと担任の先生から連絡がありました。歯医者さんに相談したところ「噛む力が弱かったり、あごの成長の未発達・虫歯や歯ぐきが弱っていると噛みづらくて食事時間が長くなります。」と教えてくれました。幸い虫歯はなかったのですが、生え変わりの時期で、ぐらぐらしてる乳歯があったので乳歯を抜いてもらいました。すると食事もしっかり噛めて給食の時間もみんなと同じ時間に食べ終わることができました。
次男は保育園で好き嫌いが多いと言われたことがありました。家では食べれる食材も保育園では食べませんでした。次男に聞くと、食材が大きくてお口に入れずらいとのことでした。保育園の先生に少し小さくカットしてもらうと喜んで給食を食べたそうです。食材の大きさや飲み込める力によっても食べる意欲や食べる時間が変わるのだと感じました。
食事に集中できない環境
我が家でごはんの前に徹底していたことは、席に着く前におもちゃや絵本などは目に入らないように片付けてから食事をしました。食べることに集中できる環境も整えていきました。
給食やお弁当など、学校・保育園では周りが騒がしいと食事が進まないことがあります。
心理的な要因・プレッシャー
お子さんの心理的な「残さず食べなければ」「時間内に食べなければ」というプレッシャーが、かえって食べるペースを落とすことも。おうちでの声掛けなども影響してきます。
また嫌いな食べ物や苦手な食材があると、手が止まりがちです。
発達特性や個性
発達の特性で、食事に集中しにくい、ペース配分が苦手というケースもあります。保健師などと相談しながら、身体の発達に合わせて食事についても慎重に進めていくことが大切です。
もちろん、定型発達でも「よく噛んで味わいたい」「マイペースで食べたい」という個性の現れもあります。
お腹が空いていない・食事量が多い
食事の直前におやつを食べていたり、食事量が多すぎると、食べる速度が落ちます。
箸やスプーンがうまく使えない
特に小学校低学年では、箸の使い方が未熟で、食べ物をうまく口に運べないことがあります。
体調や気分の変化
口内炎や歯の生え変わり、体調不良、悩みごとなども食事のペースに影響します。
私の現場体験談:食べるのが遅い子どもたち
ケース1:咀嚼回数が多すぎて1時間以上かかる小学生
ある男の子は、1食にかける咀嚼回数が平均の5倍以上。
「噛まずに飲み込むと胃腸に負担がかかる」と思い込み、1口ごとに100回以上噛んでいました。
夕食が終わるまで1時間以上かかることもあり、ご家族も困惑していました。
【対応】
咀嚼の大切さは認めつつ、「噛みすぎも体に負担がかかることがある」と説明し、30回程度を目安に「今日は何回噛めたかな?」と一緒に数えてみる遊び感覚の声かけを気長に進めました。
「噛みすぎなくても大丈夫だよ」と安心感を伝えることで、徐々に食事時間が短縮しました。
ケース2:おしゃべり好きな女の子の給食対策
保育園の現場で、食事中におしゃべりが止まらず、給食が終わらない女の子がいました。
「みんなが食べ終わるまでに食べてね」と言っても効果なし。
【対応】
食事中は「おしゃべりタイム」と「食べるタイム」を分けてみることをわかりやすい言葉で伝えました。「○分だけは食べることに集中しようね」とタイマーを使い、ゲーム感覚で取り組みました。
そして「全部食べられたら、みんなでお話ししよう!」と声かけしたところ、達成感につながり、徐々に食事時間が短縮。
ケース3:食事への執着が薄い子への工夫
年長のお子さんが、夕食に2時間かかるとのご相談。
軟らかいお菓子はすぐ食べるのに、食事には興味が薄い様子。
【対応】
食事をワンプレートにして見た目を楽しく、お子様ランチ風に工夫しました。食卓を「楽しい雰囲気」にし、会話を増やすことで食事自体への興味を引き出しました。
「決められた時間で食べ終わったらご褒美」などの声かけは効果が薄かったものの、成長とともに自然と早く食べられるようになりました。
原因別アプローチと家庭でできる具体策
口腔機能・噛み合わせの未発達への対策
-
歯科医院で定期的なチェックを受け、噛み合わせや虫歯の有無を確認。
-
奥歯や舌の使い方が未熟な場合は、歯科衛生士による口腔機能訓練も有効。
-
家庭では「よく噛んで食べてね」と優しく声かけし、親がお手本を見せる。
食事環境の見直し
-
テレビやおもちゃを片付け、食事に集中できる環境を整える。
-
食事量を無理なく食べきれる量に調整し、「全部食べられた!」という小さな成功体験を積み重ねる。
-
ワンプレートやお子様ランチ風の盛り付けで、見た目の楽しさをプラス。
心理的な負担を減らす声かけ術
-
「早く食べて」「残さないで」などの急かす声かけは逆効果。
-
「今日は○分で食べ終わったね!」「この後○○が待ってるよ」と前向きな声かけを意識。
-
食事を「リラックスできる、楽しめる場」にすることを最優先に。
発達特性や個性に合わせた工夫
-
発達や個性による場合は、「食べること自体を楽しむ」ことを重視し、無理にペースを合わせさせない。
-
箸やスプーンの使い方が苦手な場合は、練習をサポートしつつ、無理なくフォークなども活用。
「食べない状態が続いたら片付けてOK」ルール
-
3分以上食べない状態が続いたら、一度食事を片付けるのも一つの方法。
-
「食べなければ」というストレスを減らし、時間内に食べる意識を育てる工夫です。
食べるのが遅い子どもの“いいところ”も見つけよう
よく噛む・味わう・マナーが良い
-
「よく噛んでいる」「味わって食べている」ことは、消化や満腹感の面でもメリットがあります。
-
ゆっくり食べることで、食事のマナーや食材への興味が育つことも。
焦らず見守ることの大切さ
-
成長とともに食事のスピードが変化することも多いので、焦らず見守る姿勢も大切です。
まとめ:子どもの「食べるのが遅い」に寄り添うために
食べるのが遅い子どもには、口腔機能の発達、心理的な要因、個性や発達特性など、さまざまな背景が隠れています。
急かすのではなく、まずは「なぜ遅いのか」を一緒に考え、家庭や園・学校でできる工夫を少しずつ取り入れてみてください。
私自身、歯科衛生士・口育士として多くのご家庭と関わる中で、「食べることを楽しむ」ことが何よりも大切だと実感しています。
今日からできる小さな工夫や前向きな声かけで、お子さまの食事時間が少しでも楽しく、健やかなものになりますように。
【体験談・独自コンテンツを多く盛り込み、専門家視点で執筆しています】


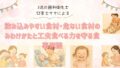
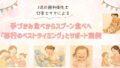
コメント