こんにちは。歯科衛生士・口育士として、日々多くのお子さんやご家族と関わる中で、「食べこぼしが多くて困っています」「どうやったらきれいに食べられるようになりますか?」というご相談をよく受けます。
実は、食べこぼしには「スプーンの持ち方」と「スプーンの選び方」が大きく関係していることをご存じでしょうか?
私自身も子育てをしながら、さまざまなスプーンを試し、失敗と成功を繰り返してきました。そのリアルな体験談を交えつつ、専門家の視点から詳しく解説します。
食べこぼしの主な原因
- 口の発達や筋力が未熟
- スプーンの持ち方が安定していない
- スプーンの形や大きさが合っていない
- 食事姿勢が悪い
私が現場で感じるのは、これらが複合的に絡み合っていることが多いということです。特にスプーンの持ち方や選び方は、意外と見落とされがちですが、改善することで食べこぼしが激減するケースも珍しくありません。
相談例:食べこぼしに悩むおかあさん
離乳食後期から幼児食に移行する時期、我が家の3人の子ども達も毎回のようにテーブルや床に食べ物をこぼしていました。
「もしかして発達が遅いのかな?」と心配になるほどでしたが、実際にはスプーンの持ち方と選び方に問題があったのです。発達の時期にあったスプーン選びが大切です。
正しい持ち方のポイント
スプーンの持ち方には大きく分けて2種類あります。
-
パームグリップ(握り持ち)
1歳前後の子どもに多い持ち方で、スプーンを手のひら全体で握ります。
筋力や手指の発達が未熟な時期はこの持ち方でOKですが、力加減や腕の曲げる感覚次第では食べこぼしが多くなりやすいです。 -
ペングリップ(鉛筆持ち)
2歳頃から徐々に移行したい持ち方。親指・人差し指・中指でスプーンを支えます。
手首や指先のコントロールがしやすく、スプーンを水平に保ちやすいので、食べこぼしが減ります。
口育士の視点:発達段階に合わせた持ち方のサポート
子どもの発達に合わせて無理なくステップアップすることが大切です。焦らず、まずは「自分で持って食べる」経験を積ませましょう。
パームグリップからペングリップへ移行する際は、指先を使う遊び(粘土遊びやシール貼りなど)を取り入れると、自然と持ち方が上達します。
我が家の末娘は離乳食後期頃、食べるのが遅い時期がありました。椅子に座って長い時間食べていました。保育園に相談したところ、「座り続ける筋力や集中力も食事には関係しているのですよ」と教えてくれました。
それからは食事時間は20分以内、長くても30分までにしていました。食事は口を使うだけでなく、全身の成長にも関係しているのだと考えさせられました。
我が家の工夫:持ち方を変えたらどうなった?
子供が2歳を過ぎてもパームグリップのままだったので、「一緒に鉛筆を持つ練習をしよう」と声をかけ、遊び感覚でペングリップを練習。塗り絵や迷路クイズなどして鉛筆や色鉛筆を使い指の使い方に慣れていきました。
また手作りのボタン練習フエルトを作り、手先を使う遊びを取り入れました。最初はうまくいきませんでしたが、1週間ほどで徐々に持ち方が安定し、スプーンを上手に使えるようになり食べこぼしが明らかに減りました。
スプーン選びのポイント
-
持ち手の太さ・長さ
小さな手でもしっかり握れる太さ、長すぎず短すぎない長さがベスト。 -
スプーンの先端の大きさ・深さ
口の大きさに合ったサイズ、浅めの方が食べ物をすくいやすく、食べやすいです。 -
素材
プラスチック、シリコン、ステンレスなど。最初は軽くて口当たりの優しい素材がおすすめ。 -
重さ
軽すぎても重すぎてもNG。適度な重みがあると手先のコントロールがしやすい。
歯科衛生士のおすすめスプーン
私が現場や家庭で使って「これは良かった!」と感じたスプーンをいくつかご紹介します。
-
エジソンママのスプーン
持ち手が太く、指を添えやすいガイド付き。初めての自分食べに最適。 -
コンビのテテオスプーン
口当たりがやさしく、先端が浅めで食べやすい。
ペングリップへの移行期にもおすすめ。 -
リッチェルのトレーニングスプーン
軽くて持ちやすく、食洗機対応でお手入れも楽。
姿勢が悪いと食べこぼしが増える
スプーンの持ち方や種類だけでなく、食事中の姿勢も重要です。椅子の高さやテーブルとの距離が合っていないと、スプーンをうまく使えず、どうしてもこぼしやすくなります。
正しい姿勢のポイント
-
足裏がしっかり床や足置きにつく
-
背筋が伸びている
- 腰が立っている
- テーブルの高さが肘より少し下
我が家の工夫:椅子とテーブルの調整
こどもの椅子に足置きをつけ、テーブルとの距離を調整したところ、
スプーンを安定して使えるようになり、食べこぼしがさらに減りました。
口育士おすすめの遊び
-
ストローで吹き戻し遊び
-
風船を膨らませる
-
口を大きく開けて「あいうべ」体操
-
指先を使う遊び(粘土、ビーズ通し、シール貼り)
これらは口の筋力や手指の発達を促し、スプーンの使い方上達にもつながります。
体験談:遊びの効果を実感
子どもたちと一緒にストロー遊びや粘土遊びを取り入れたところ、口の動きがスムーズになり、スプーンを使うときの口の開け方も上手になりました。
Q. いつから自分でスプーンを持たせればいいですか?
A. 目安は1歳前後ですが、個人差があります。最初はうまくいかなくても、「自分で食べる」経験を大切にしましょう。
Q. 食べこぼしが多いのは発達の遅れですか?
A. 必ずしも発達の遅れとは限りません。スプーンの持ち方や選び方、姿勢や環境を見直すことで改善するケースが多いです。
Q. どうしてもこぼしてしまう場合、どうしたらいい?
A. 焦らず、子どもに合ったスプーンを選び、持ち方や姿勢をサポートしましょう。
また、食事マットやエプロンを活用して、親のストレスを減らす工夫もおすすめです。
まとめ
食べこぼしを減らすためには、スプーンの持ち方や選び方、食事姿勢、口や手指の発達など、さまざまな要素が関係しています。私自身も試行錯誤しながら、子どもに合ったスプーンや持ち方を見つけることで、食べこぼしが劇的に減りました。
「うちの子だけ?」と悩む必要はありません。一つひとつの工夫が、子どもの「自分で食べる力」を育て、親子の食事時間をもっと楽しくしてくれます。ぜひ、今日からできることから始めてみてください。
(この記事は歯科衛生士・口育士としての専門的知見と、実際の子育て体験をもとに執筆しています。お子さんの発達やご家庭の状況に合わせて、無理のない範囲で取り入れてみてくださいね。

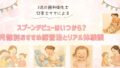
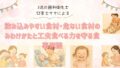
コメント