「うちの子に限って」と思いがちな窒息事故ですが、実は誰にでも起こり得る身近な危険です。私自身、長男が食事中にリンゴを喉に詰まらせ、顔色が変わった瞬間の恐怖は今も忘れられません。
あの時、すぐに背中を叩いて異物を出せたから大事には至りませんでしたが、ほんの少しの油断が命に関わることを痛感しました。この記事では、実体験を交えながら、食事中の窒息事故を防ぐための注意点と、万が一の時の対応法を詳しくお伝えします。
窒息事故が起きやすい食事シーンと原因
子どもや高齢者に多い理由
窒息事故は、特に小さな子どもや高齢者に多く発生します。子どもはまだ噛む力や飲み込む力が十分ではなく、つい丸のみしてしまいがちです。高齢者は飲み込む機能が衰えているため、食べ物が喉に詰まりやすくなります。
危険な食べ物とその特徴
窒息事故の原因となる食べ物は意外と身近にあります。餅やご飯、パン、飴、団子、リンゴ、ブドウ、ミニトマト、ナッツ類、こんにゃくゼリーなど、普段よく食卓に並ぶものばかりです。丸くてつるっとしたもの、弾力があるもの、水分が少なくパサパサしたもの、噛み切りにくいものは特に注意が必要です。
体験談:
私の家庭でも、餅やごはん、パン、飴、団子、リンゴ、ぶどう、ミニトマト、ナッツ類、こんにゃくゼリーなどでヒヤッとした経験があります。特に長男がりんごを大きなまま口に入れてしまい、のどにつかえそうになったときは、本当に焦りました。
丸くてつるっとしたものや、弾力があって噛み切りづらいは、子どもがのどに詰まらせやすいと実感しています。
食事中に守るべき注意ポイント
食べ物の選び方と与え方
我が家では、ブドウやミニトマトは必ず縦に四つ割りにして、パンも1㎝角にカットしていました。以前末っ子がパンを大きなまま口にほおばってしまった時は、飲み込めずに咳き込んだことがありました。それ以来、子ども達が自分でちぎって食べるときも、「このくらいの大きさだと安心だよ」と声をかけています。
飴や団子、ナッツ類は、子ども達が大きくなるまで絶対に与えませんでした。

食事環境と姿勢
おやつをリビングでゴロゴロしながら食べていた時、末っ子が何度も「オエッ」と戻しそうになったことがあります。それ以来、必ず椅子に座り、足台で足がしっかりつくように調整。姿勢が安定すると、飲み込みもスムーズになったと感じています。「ながら食べ」はしないように、テレビを消して家族を囲むようにしています。
食べ方の指導と見守り
保育園で働いていた時、給食後には必ず「ごちそうさまの後にお口を見せてね」と声をかけていました。上顎にパンがくっついていた子もいて、これを見逃して遊び始めると危険だと何回も感じることがありました。
窒息事故が起きたときの緊急対応
窒息のサインを見逃さない
実際に、長男が餅をのどに詰まらせた時は顔が真っ白になり、唇が紫色に変わりました。声も出せず、目が宙を見ていたので「これはただ事じゃない」と直感し、すぐに背中を叩いて異物を出しました。こうしたサインを見逃さないことが本当に大切だと痛感しています。
まとめ:命を守るためにできること
私自身、子どもの窒息体験や保育現場でのヒヤリとした瞬間を通じて、「小さく切る」「食事は落ち着いた環境で」「最後にお口チェック」を徹底するようになりました。家族みんなでルールを共有し、もしもの時は慌てずに対応できるよう練習もしました。命を守るのは、親の直感と冷静な対応そして日々の積み重ねだと強く感じています。
長男がパンを大きなまま口に入れて咳き込んだ経験から、パンやごはんは一口サイズを意識しています。
食事中は必ず私か夫がそばにいて、子どもの様子を見守るようにしています。
昔、友人の家でナッツを食べて窒息しかけた話を聞いて以来、ナッツやこんにゃくゼリーなど危険な食品は小さいうちは絶対に与えませんでした。
子どもたちの笑顔を守るために、小さいことですが意識していきましょう。

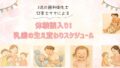
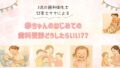
コメント