「フッ素ってよく聞くけれど、本当のところどう使えば効果的なの?」「子どもに使っても安全なの?」――そんな疑問を抱く方は多いのではないでしょうか。
私自身、3人の子どもを育てながら歯のケアに悩んできました。歯科衛生士の経験と母としての実体験をもとに、無理なく続けられるフッ素ケアのコツをお話しします。
フッ素とは?虫歯予防の仕組み
フッ素は歯科分野で注目される成分で、毎日の水道水にも微量に含まれています。また海水や海藻にも含まれ天然のミネラルの成分の一つです。
歯の表面に作用し、溶けかかった歯を補修しやすくする「再石灰化」という現象を促します。また歯を覆う薄い保護膜を強化し、酸による損傷を減らす働きがあります。私の長男は野菜嫌いで食物繊維の摂取量も少なかったため、定期的なフッ素ケアの重要性を歯科医師から直接説明されました。
これらの作用が積み重なることで、虫歯に負けにくい“強い歯”を作ることができます。私の子どもたちも、定期的なフッ素ケアのおかげで虫歯ゼロを継続中です。
フッ素を使う人・使わない人の違い
同じ学年の子ども同士でも「夜にフッ素入り歯磨き剤を使う/使わない」で、検診時に虫歯の本数が異なっていました。
長男がフッ素入り歯磨き剤を使い始めてから定期健診で「虫歯もなく、歯の表面は硬くつるつるしていてとてもきれいです」と言われ、効果を実感。一方まだ使っていなかった末娘は健診で、「歯の表面に小さいですが初期虫歯の跡が見つかりました」と言われました。本人や私もとてもショックでした。それからコツコツフッ素を取り入れて、虫歯になることはありませんでした。
歯にフッ素の鎧(よろい)を着せてあげることで、虫歯菌がエナメル質に入らないようにします。このタイミングでフッ素習慣をつけることで、思春期以降の虫歯リスクを大幅に減らせます。
フッ素の取り入れ方
フッ素入り歯みがき剤を使う
我が家で使っている歯みがき剤は「子ども用は約900ppm」「大人用は約1450ppm」と成分表示で確認しています。歯科医師から「うがいでフッ素を洗い流さないのがポイント」と教わり、歯磨き剤の後のうがいは1回だけにしています。
夕食後に子ども全員で一緒に使うタイミングをつくっています。市販の歯みがき剤によっても味や泡立ちが違うため、子どもが選んだ商品を使うことで楽しみながら継続できました。

フッ素洗口(うがい)を取り入れる
小学校低学年のころから家で「フッ素洗口」を始めました。最初は味や習慣に慣れず嫌がる時期もありましたが、シール表を作って「1週間ごとに目標達成でプレゼント方式」にしたら自発的に続けられるように。歯科医院では担当歯科衛生士さんに「前回より歯垢が少なくなった」と具体的な評価を伝えてもらい、子ども自身が自信を持てるきっかけに繋がりました。
歯科医院での高濃度フッ素塗布
家庭ケアを補う“スペシャルケア”として、3〜4か月に一度、歯科医院でフッ素塗布を受けましょう。歯科衛生士が歯の状態をチェックしながら施術するため、虫歯の早期発見にもつながります。定期検診と一緒に受けるのが理想的です。
我が家でも3か月に一度定期健診で虫歯のチェックと歯みがきができてるかのチェックもしてもらってます。そして最後に歯科医院でしか塗れない高濃度フッ素を塗布して健診終了です。子ども達も定期的に歯科医院に通院しているので、歯医者さんに嫌がることもなく楽しく通えています。
年齢別フッ素ケアのポイント
0〜3歳(乳幼児期)
歯の成長段階をよく観察し、定期的に歯科健診で専門家に相談するのが安心です。歯みがきジェルはサイズだけでなく「子どもが嫌がらない味」を優先しました。この時期は歯みがき習慣をつける、歯科への定期健診のきっかけなど虫歯ゼロの大切な時期になります。
4〜12歳(幼児〜学童期)
5歳になった息子はジェルの甘さが苦手だったので、無香料タイプにしてみました。するとあっさりすすんで自分から歯みがきジェルを手にとっていました。子どもの好みも出てくる時期です。その子に合った虫歯ゼロを目指していきましょう。

写真は次男が小学生のとき、お友達が泊まりにきて染め出し大会をして、楽しく磨き残しチェックをしていました。意外とどのご家庭でも磨き残しは多かったです。
4~12歳では、兄弟で「うがいレース」でケアの楽しみを作り、徐々にフッ素洗口へ移行し毎日続けることができました。

13歳以上〜大人
中学生以降は、反抗期で親の指示を嫌う傾向が強くなるため、自分の選択で歯みがき剤を選ばせたら、進んで夜のケアをするようになりました。また歯科医院の健診も○○休みなどの長期休みのときに予約をして定期健診も通いやすく工夫すすこともおすすめです。
我が家の3人の子どもたちは、仕上げ磨きのいらない年齢になりましたが、歯磨きの大切さを実感しているのか、歯みがきの時間はしっかり時間をかけて自分で磨いています。
甘い飲み物や間食が多い方は、夜の歯磨きでじっくりと時間をかけることが大切です。高濃度のフッ素の歯磨剤を使い、うがいは1回くらいにしてフッ素が口の中に残るようにするのも効果的です。歯科衛生士としての経験からも、虫歯ゼロの方ほど「就寝前の磨き方」が丁寧です。
高齢期
唾液量の減少によって、歯の根元に虫歯(根面う蝕)ができやすくなります。フッ素ジェルや洗口剤を活用して、歯茎付近を丁寧にケアしましょう。介護施設でもフッ素ケアを導入するところが増えており、口腔トラブルの予防に役立っています。
実家の母にもフッ素歯磨剤を勧めたところ、「子どもじゃないからもう虫歯にはならないわよ」と言っていたのですが、定期健診で歯医者さんに、年齢を重ねると、子どもは虫歯にならない部位が虫歯になっていきます、といわれたようです。それからは虫歯予防と歯周病予防の両方に気をつけています。
フッ素の安全性について
「フッ素の安全性」に関して、心配な方も多いですが、国内歯科医療機関の基準では幼児にも1回分量を守れば心配不要です。実際担当歯科医師から「過剰摂取リスクは市販品では起こりえない」と聞いています。2025年現在、厚生労働省やWHOでは子どもの虫歯予防での使用推奨が強調されています。
一回分量など詳しくはこちらをご参考に
https://www.mhlw.go.jp/content/001037973.pdf
まとめ:続けるほど、違いが出る
フッ素ケアは、子ども自身が興味を持てる工夫(シール作戦・商品選び・一緒にケア)などで無理なく続けるのが最大のコツです。過去の失敗や成功談を活かして、家庭ごと・子どもごとに合ったルールとやり方を探してみましょう。
将来、子どもが自分で歯の「健康習慣」をコントロールできる力を持つためにも、楽しい歯みがきタイムを大切にしましょう。
歯科衛生士・3児の母からのメッセージ
フッ素ケアは1日で結果が出るものではありません。数年後、そして将来の健康な歯のための投資です。今日からできる小さな習慣が、5年後、10年後に確実な違いを生み出します。無理をせず、自分や家族に合った方法でフッ素を取り入れていきましょう。目には見えない違いですが、毎日のエナメル質ケアは将来の白い歯を手に入れる近道になると信じています。

写真は我が家で毎日使っている歯科専売の高濃度フッ素入り歯磨剤です。泡立ちすぎず、味も強くなく磨きやすく、続けやすいです。我が家は10年近くコレです!味や性状(ジェル・ペースト・フォームタイプ)ドラッグストアにいくと色々あり迷ってしまいますが、歯科医院で相談したり、試供品など試させてもらい楽しく続く習慣ができるといいですね。目指せ永久歯虫歯ゼロ!!

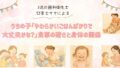
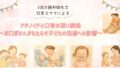
コメント