私の長男も冬になると「お口がカラカラする」「唇がひび割れて痛い」と訴えることが多く、親としてどうサポートすればいいのか悩みました。また暑い時期は部屋の中にいても汗びっしょり。麦茶が子ども三人ですぐ無くなっていました。
この記事では、実体験を交えながら、口が乾いたり、身体が水分不足になると口の中はどんな変化が起きるのか、口腔乾燥対策や唾液分泌を促すコツ、家庭でできる保湿ケアについて詳しくご紹介します。
なぜ子どもの口が乾きやすくなるのか
季節や生活習慣の影響
「ママーのど乾いた!」と暑い夏にグビグビ飲んでいると、「暑いからのど乾くね」と麦茶をたくさん作りました。でも冬でも「のど乾くー。」と子どもは言ってきます。実はエアコンや乾いた空気の中では子どもは口が乾くのだなと感じました。また春もよくのどが渇いていました。長男はスギ花粉症だったので、鼻づまりなどの花粉症の症状が出ると、口で呼吸するので口が乾いていました。1年を通して比較的に口は乾きやすい環境なんだと改めて感じました。
唾液の役割と分泌が減るリスク
口やのどが渇くことと、虫歯になりやすさは関係ないと思っていましたが、長男の花粉症の症状がひどい時に歯科健診に行ったときに「口が乾くと、虫歯になりやすいんだよ。今は虫歯になっていないけど、唾液には虫歯抑制や歯を強くする力をもっているんだよ」と歯医者さんに言われました。そこでハッとしました。
花粉症のない次男はおやつ食べた後、口の中におやつは残ってないことが多かったです。長男は口が乾いている時はおやつが歯に残っていることが多かったです。これが虫歯になりやすさになっていくんだろうなあと感じました。
口腔内の保湿ケアの工夫
リップクリームや保湿剤の活用
長男の仕上げ磨きをするときに、「大きく口開けて」というと、「口が痛くて開けられない」というのです。よく見ると、唇が乾燥してひび割れていて、ひび割れたところから出血していました。できる範囲での歯みがきをしました。
それからはリップクリームを塗ったり、唇をいじりすぎたりしないように気にしてみると少しづつ唇の乾燥も落ち着いてきました。リップを塗るタイミングもすぐなめてなくならないように、寝る前や食事前などタイミングを見ながら塗るようにしていました。
マスクで湿度を保つ
冬場の外がとても乾燥しているときは、子ども達が「口の中がヒリヒリする。」というくらい口の中が乾燥していました。そんな時はマスクをしていました。マスクをしてしばらくすると保湿されて口の中が楽になったのか、「痛くなーい」とマスクの重要性を感じました。キシリトール入りの飴をなめるのも口が乾きづらくなるので小学生くらいになったらやってみてください。
加湿器や室内環境の工夫
冬の寒い日は外で遊ばずに家の中で遊ぶこともありました。遊んでいると「口が乾く!」と3人で言いにくることが多かったです。室内の乾燥も子ども達にはつらい環境なのだと気づかされました。そこで加湿器をつけて、部屋の湿度をあげていくと、また元気に三人で室内遊びを楽しんでいました。
湿度をあげるには、洗濯物を干したり、キッチンでお湯を沸かしたりするのも、手軽に湿度をあげられる方法です。
唾液分泌を促すための生活習慣
水分補給をこまめに
子どもはいつでも活動的!我が家の3人もいつでも元気いっぱいでした。のどが渇いたと感じる前に麦茶で水分補給をしていましたが、ある時水分補給後、次男が麦茶を戻してしまいました。小児科の先生に相談すると「病気ではありません。子どもの胃は小さいので少しずつ水分を補給するように注意してあげてくださいね」と言われました。
ごくごく飲みたい分だけあげるのではなく、こまめに少しずつの水分補給に切り替えました。暑い夏などは寝室に水筒を持っていき、夜中寝苦しくて起きてしまったときに、少し水分をあげるだけで、また静かに眠ることもしばしばありました。少しずつこまめにを今でも意識しています。
よく噛んで食べる
食事の際は、よく噛んで食べることで唾液腺が刺激され、唾液の分泌が増えます。柔らかいものばかりでなく、噛みごたえのある食材を取り入れるのもおすすめです。
私の家庭では、野菜スティックやおにぎりを大きめに握るなど、噛む回数が増える工夫をしています。
ガムや昆布で唾液腺を刺激
ガムを噛める年齢の子どもには、キシリトール入りのガムや、だし昆布を口に含むことで唾液腺が刺激され、唾液分泌が促進されます。
私も子どもと一緒にガムトレーニングを試したところ、「お口が潤う感じがする」と喜んでいました。
ただしキシリトールは多く摂取しすぎると、お腹がゆるくなることがあるので、適量にしましょう。
舌や口周りの体操
唇が閉じているか、開いているかで、口の乾き方は全然違います。唇も筋肉です。唇の力を鍛えて口を閉じるようにしましょう。
舌を大きく動かす運動や「あいうべ体操」など、口周りの筋肉を鍛える体操も効果的です。舌を前に出したり、唇をなめるように回したりすることで、唾液腺が活性化されます。
食前に親子で「あいうべ体操」を取り入れると、食事中の唾液分泌がスムーズになりました。
リラックスする時間を作る
ストレスや緊張が続くと、唾液の分泌が減りやすくなります。お子さんがリラックスできる時間や、好きな遊びを取り入れて、心身ともにゆったりと過ごすことも大切です。
口呼吸の改善も大切
鼻呼吸を促すトレーニング
鼻づまりなどで口呼吸が増えている場合は、鼻呼吸を促すトレーニングも有効です。深呼吸や鼻を通すエクササイズ、ガムトレーニングなどを取り入れることで、自然と口呼吸が減り、口腔乾燥の予防につながります。
睡眠時の工夫
次男が歯科健診の時に、歯医者さんの先生に「寝ている時は口は閉じているようにすると虫歯になりにくいから、枕の高さや鼻づまりや口テープなんか色々工夫してみてね」と教えていただきました。次男は熟睡すると口が開いていたので、夜中口が乾いて起きることはあったので、口テープを上下の唇に貼って寝たところ、翌朝のど乾かなかった!とすっきり起きられたようでした。
私自身は寝る前に鼻の通りを良くするためのスチーム吸入を取り入れたところ、朝の口の渇きが軽減しました。
体験談:我が家の乾燥対策チャレンジ
冬になると息子の唇がひび割れ、口の中もカラカラになりがちでした。最初はリップクリームや保湿剤を塗っても、すぐに舐めてしまい効果を感じられませんでしたが、寝る前と朝起きた時に塗るようにしたら、ひび割れが改善。加湿器を使い始めてからは、朝の口の乾きもだいぶ和らぎました。
また、食事の時に「よく噛んで食べようね」と声をかけたり、キシリトールガムをおやつに取り入れたり、親子で「あいうべ体操」を続けることで、息子自身も「お口が潤ってきた」と実感できるようになりました。水筒を持ち歩く習慣も、外出先や学校でも口の乾きを防ぐのに役立っています。
まとめ
子どもの口が乾きやすいと感じたら、まずは生活環境や習慣を見直し、保湿と唾液分泌アップの工夫を取り入れてみましょう。
リップクリームやマスク、加湿器などで外部からの乾燥を防ぎつつ、よく噛む食事や舌体操、水分補給、リラックスした時間を意識することで、口腔内の潤いを保つことができます。
家族みんなで楽しく続けられる方法を見つけて、健やかな口腔環境を守りましょう。
(この記事は実体験と最新の歯科・医療情報をもとに執筆しています。気になる症状が続く場合は、必ず歯科医師や小児科医にご相談ください。)

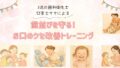
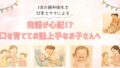
コメント