コロナ禍も過ぎ、マスクを外すことが多くなり、口元が再注目されています。白くて歯並びのいい笑顔は誰でも憧れます。
我が家でも子ども達に少しでも歯並びよく育ってほしい、噛み合わせをきれいに整えたいと思い、小さい頃から取り組んできたことがあります。こちらでは、おうちで歯並びのためにできることを実体験を交えながらご紹介します。
噛みグセが歯並びに与える影響
どんな癖が歯並びを悪くするのか
長男は我慢をするときや、悔しい時は泣くよりも下唇を噛む癖がありました。気づくと下唇を噛んでいました。ある日夫が仕上げ磨きをしていると「下の前歯が歯並びガタガタしてきてる」と心配していました。よく見ると、確かに下の歯並びが内側に入り込んで、ガタガタした歯並びになっていました。歯科健診で歯医者さんに診てもらうと、虫歯の心配はないけど、歯並びは悪くなっているとのことでした。
歯医者さんで、日頃の口元の癖や食べ方など聞かれました。すると下唇を噛むのが原因とのことでした。まさか唇を噛むだけで。歯並びが悪くなるなんて思ってもいなかったのでびっくりしました。ほかにも、指しゃぶり・おしゃぶり・爪噛み・片側だけで噛む・口呼吸も歯並びが悪くなる原因と歯科医院で言われました。日頃のちょっとしたことで歯は動くんだなあと驚いたのはよく覚えています。
唇や舌の癖がもたらすリスク
歯を矯正装置で動かす力は100gほどです。舌の重さは筋肉なので、500gとずっしりしています。舌の力が毎日加わると、簡単に歯は動きます。
次男は口を開けて、ベロを唇に乗せる時期がありました。最初は気にしてなかったのですが、もしかしたらこれも歯並びによくないのかもと思い見てみると、歯並びが2本の前歯だけビーバーのように出てしまっていました。子どものこんな小さい舌の動きでも歯は動いてしまうのだなと今でも戒めになっています。
噛みグセが定着するきっかけ
末っ子娘が生まれたとき、次男はまだ2歳でした。幼児食を次男が自分で食べてる時もありました。すると片方だけの奥歯でクチャクチャ噛んでいることが多かったです。歯科健診の時に先生は奥歯の歯並びを見て、「いつも同じ側だけでクチャクチャ噛んでいませんか。歯並びに偏りが見られます。噛む癖はストレスなどでも影響されます」と言われました。
片方ばかりで噛むこと・ストレスが噛み合わせにも影響するのだと歯科健診で教えてくれました。今でも食卓みんなで楽しい食事を意識しています。
歯並びを守るための噛みグセ改善トレーニング
日常でできる意識改革
我が家の3人の子ども達のそれぞれ口元の癖は違っていました。長男は唇を噛む癖・次男は舌を唇に乗せる癖・末っ子はおしゃぶりが大好きでした。子どもによって、口元の癖には個性があり、人によって違うのだなあと感じていました。
小さな癖でも毎日続けていると、歯や顎に大きな力がかかり、長い目でみると歯並びを悪くしていくのだと実感しています。まずこどもがどんな癖を持っているかを観察することから始めるのが大切です。
舌と口周りの筋肉を鍛えるトレーニング
我が家の子どもそれぞれ口元の癖が違うのですが、共通していることにある日ハッと気づきました。唇も舌も筋肉だ!力で動いたなら、力でもとに戻せるかも!と子ども達をみて思いました。
それからは、お風呂で湯舟に浸かって、数を数えるときに必ず唇をしっかり閉じて舌をぐるぐる回す「舌回し」を根気強く続けました。また歯みがきのあとは、頬ふくらまし風船大会をして頬を口いっぱい膨らますという遊びながら頬の筋肉を積極的に使うようにしました。
正しい舌の位置を覚える
「ママ!ベロが上についた!」と長男が口の中を見せてきました。歯科健診の時、歯医者さんに「ベロは上のあごの前歯のうらについてるのがいいんだよ!」といわれたのを覚えていたようで毎日ベロ回しをしていたらベロが上あごについてきたと教えてくれました。本人も練習していたことができるようになったのがうれしかったようで、毎日続けてベロ回しを頑張っていました。
よく噛んで食べる習慣をつける
我が家の子ども達はカレーが大好きでした。よく作っていましたが、家族で食べていると子ども達はあまり噛まないで飲み込んでいることに気づきました。食材やメニューでもお口のトレーニングになるかもしれないと思いました。
それからはゴボウやスティック人参・ほしいもやシャキシャキのもやしなどよく噛む食材を使ったメニューやおやつを食べるようにしました。子ども達も最初は噛めない!硬い!など言っていましたが、甘しょっぱく味付けて子どもの好きな味にすることで、おいしい!とよく食べてくれるようになりました。
噛みグセを防ぐ生活習慣の工夫
我が家の食卓のテーブルは私が端っこに座る席順でした。子ども達は、ママである私の方を向きながら、食べたり話したりしていつも同じ席で食べていました。歯科健診のとき「噛み合わせに偏りが見られるのですが、食卓などいつも同じ向きだと姿勢や噛み合わせも偏ってきますよ」と言われました。目からうろこの指摘でした!確かに私の方ばかり見て、子ども達は食べていました。
それからは夫も含めた家族5人で毎週席替えをして、色々な席で家族で食べるようにしました。食べる姿勢や向きで噛み癖が影響しているのだと理解できました。
歯科医院でできるサポートと相談
筋機能療法(MFT)の活用
自分だけで癖を直すのが難しい場合は、歯科医院で筋機能療法(MFT)を受けるのもおすすめです。専門のトレーニングや装置を使い、舌や口周りの筋肉の使い方を正しく指導してもらえます。
私の医院もお口だけだはなく、正しく鼻呼吸できるようにする口腔周囲筋トレーニングがあります。
早めの相談が大切
歯並びや噛み合わせの乱れは、早い段階で気づいて対策を取ることが大切です。気になる癖があれば、遠慮せずに歯科医院に相談しましょう。「ちょっと気になるな」と思ったタイミングで受診することで、早めに対策ができ、歯並びの悪化を防ぐことができます。
まとめ
噛みグセや口周りの癖は、ゆっくりと知らぬ間に歯並びや噛み合わせに影響を与えていることを3人の子どもの子育てで強く感じました。お子さんの癖を見直し、日常生活でできるトレーニングや意識改革を続けることで、歯並びを予防できることを実感しています。
私自身も体験したように、家族で協力しながら癖を改善していくことが、健康な歯並びへの第一歩です。気になる癖があれば、早めに歯科医院に相談し、専門家のアドバイスを受けながら取り組んでみてください。
(この記事は実体験と最新の歯科情報をもとに執筆しています。歯並びや噛み合わせが気になる場合は、歯科医師にご相談ください。)

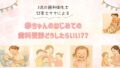
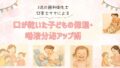
コメント