- はじめに
- 手づかみ食べからスプーン食べへ―なぜこの移行が大切なのか
- 手づかみ食べの役割
- スプーン食べの意義
- スプーン食べへの移行のタイミング
- 一般的な目安
- わが家のケース
- タイミングを見極めるサイン
- スプーン食べをサポートするための基本ステップ
- スプーンに慣れる環境づくり
- 食べやすいメニュー選び
- 具体的なサポート方法
- モデルを見せる
- 手を添えて一緒にやってみる
- できるだけ「見守る」
- スプーン食べ移行期のよくある悩みと解決策
- 「全然スプーンを使いたがらない」
- 「スプーンを投げてしまう」
- 「うまくすくえず、イライラしてしまう」
- 歯科衛生士・口育士の視点から見る「スプーン食べ」のポイント
- 口腔機能の発達とスプーン食べ
- スプーンの選び方
- わが家の「スプーン食べ」移行ストーリー
- 手づかみ食べ全盛期
はじめに
離乳食が進むにつれて、多くのご家庭で「手づかみ食べ」から「スプーン食べ」への移行が話題になります。私自身も歯科衛生士・口育士として、そして3児の母として、この時期の子どもの成長や悩みに日々向き合ってきました。
この記事では、専門家としての知識と、実際にわが子と歩んだリアルな体験談を交えながら、スプーン食べへの移行のタイミングやサポート方法を詳しくご紹介します。
手づかみ食べからスプーン食べへ―なぜこの移行が大切なのか
手づかみ食べの役割
手づかみ食べは、子どもが自分で食べ物を認識し、つかみ、口に運ぶという一連の動作を通して、五感や手指の発達、さらには「食べること」への興味を育てる大切なプロセスです。
私の息子も、9か月ごろからバナナやおにぎりを手でつかんで食べていました。最初はぐちゃぐちゃになり、テーブルも床も大惨事…。でも、この経験が「自分で食べる力」の土台になりました。
スプーン食べの意義
スプーン食べは、手指の巧緻性や口の発達、社会性の成長に直結します。
スプーンを使うことで、食べ物をすくう・運ぶ・口に入れるというさらに細かい動きが必要になり、脳や筋肉の発達を促します。
また、外食や集団生活でのマナー習得にもつながります。
スプーン食べへの移行のタイミング
一般的な目安
多くの専門書や育児サイトでは、1歳前後からスプーンに興味を示し始め、1歳半ごろには自分でスプーンを使いたがる子が増えるとされています。
ただし、これはあくまで目安。実際には、子どもの発達や性格、家庭の環境によって大きく異なります。
わが家のケース
私の息子の場合、10か月ごろからスプーンに強い関心を示し始めました。
きっかけは、私が食事中に「ママもスプーンで食べてるよ」と声をかけたり、息子の手元にスプーンを置いてみたりしたことでした。
最初はスプーンをおもちゃのように振り回すだけでしたが、徐々に「すくってみたい」という意欲が芽生えたのを感じました。
タイミングを見極めるサイン
-
食べ物を手でつかむ動作が上手になってきた
-
大人や兄弟がスプーンを使っているのをじっと見ている
-
スプーンやフォークに手を伸ばす
-
食事中の集中力が高まってきた
これらのサインが見られたら、スプーン食べへの移行を意識してみましょう。
スプーン食べをサポートするための基本ステップ
スプーンに慣れる環境づくり
最初は「食べる道具」として認識できなくてもOK。わが家では、食事のたびに息子の手元にスプーンを置き、自由に触らせていました。
時にはスプーンをカチカチ鳴らして遊んだり、食器を叩いたり…。この「遊び」の中で、自然とスプーンに親しみを持つようになりました。
食べやすいメニュー選び
スプーンの練習には、すくいやすい・まとまりやすいメニューが最適です。私がよく作ったのは、下記のようなメニューです。
-
おかゆやリゾット
-
かぼちゃやさつまいもなどのマッシュ
-
とろみのあるスープ
-
小さめの肉団子やつみれ
これらはスプーンですくいやすく、こぼれても片付けがラクなので、親子ともにストレスが少なかったです。
具体的なサポート方法
モデルを見せる
「ママもこうやって食べるよ」と、実際にスプーンで食べる様子を見せました。息子は私の動きをじっと観察し、真似したがることが多かったです。
手を添えて一緒にやってみる
最初はスプーンをうまく持てず、すくう動作もぎこちないもの。
そんな時は、息子の手にそっと私の手を添えて、一緒に「すくって、運ぶ」動作を繰り返しました。うまく口に入った時は、「できたね!」とたくさん褒めて自信につなげました。
できるだけ「見守る」
子どもが自分でやりたい気持ちを大切にしたいので、失敗してもすぐに手を出さず、見守ることを意識しました。
こぼしても「大丈夫、練習中だもんね」と声をかけ、親子で笑い合いながら進めました。
スプーン食べ移行期のよくある悩みと解決策
「全然スプーンを使いたがらない」
わが家でも、最初はスプーンに見向きもしない日が続きました。そんな時は無理に使わせず、手づかみ食べをたっぷり楽しませました。
ある日突然、スプーンに興味を示し始めたので、「その子のペースを大切にする」ことが一番だと実感しました。
「スプーンを投げてしまう」
息子もスプーンを投げて遊ぶ時期がありました。これは「物を投げるとどうなるか」を確かめている成長の一環です。
「スプーンは食べる道具だよ」と繰り返し伝え、投げた時は静かにスプーンを拾い、また手元に戻す…を根気強く続けました。
「うまくすくえず、イライラしてしまう」
スプーンで食べ物をすくうのは大人が思う以上に難しい動作です。
イライラしてしまう時は、すくいやすいメニューに変更したり、スプーンの形状を変えてみたりしました。また、「すくえなくてもOK」と親が気持ちに余裕を持つことも大切です。
歯科衛生士・口育士の視点から見る「スプーン食べ」のポイント
口腔機能の発達とスプーン食べ
スプーン食べは、口唇や舌の動き、咀嚼力の発達にも大きく関わります。
スプーンを口に運ぶことで、唇を閉じてすくう、舌で食べ物を取り込む、咀嚼する…という一連の動作が自然と身につきます。
特に、スプーンを「前歯でかじり取る」のではなく、「唇でしっかり取り込む」ことを意識してサポートするのがポイントです。
スプーンの選び方
スプーンは子どもの口の大きさや手の発達に合ったものを選ぶことが大切です。私が選んだポイントは以下の通りです。
-
口に入れやすい小さめのヘッド
- 浅いくぼみのスプーン
-
持ちやすい太めのグリップ
-
安全な素材(シリコンやプラスチックなど)
実際に数種類を試し、息子が一番使いやすそうなものをメインにしました。
わが家の「スプーン食べ」移行ストーリー
手づかみ食べ全盛期
息子が10か月のころ、毎日手づかみで食べるのが大好きでした。おにぎり、パン、蒸し野菜…。手も顔もベタベタになりながら、満足そうに食べる姿は今でも忘れられません。食後の片付けは大変でしたが、「今しか見られない成長の証」と思い、写真や動画をたくさん残し、今でも時々見ると、反省や懐かしい気持ちでいっぱいです。
そんな彼も今年就職しました。なんでもよく食べる元気な男の子に育ちました!!

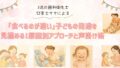
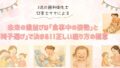
コメント