はじめに
子ども達をふっと見ていると、「あれ?口がぽかんとあいているな」「朝、口臭してるかな?」と子ども達の口の気になることが増えました。
そのころ私の勤務している歯科医院でも同じような相談をするお母さんが増えてきました。虫歯はなくてもお口が普段あいているのは、口にとってはよくないことだよと、歯医者の先生はいつも言っています。
しかし、正しい知識と実践で、体調や見た目が大きく変わります。本記事では、口呼吸がもたらす影響と、私の実体験を交えた今日からできる改善法を詳しく解説します。
口呼吸とは?知られざるその実態
口呼吸の特徴と原因
口呼吸とは、鼻ではなく口から空気を吸ったり吐いたりする呼吸方法です。無意識のうちに口が半開きになっていたり、寝ている間にいびきをかいていたりする人は、口呼吸の可能性が高いです。
我が家の長男も3歳くらいの時、口で呼吸しているようで、食事しているとき口が閉じていると鼻で呼吸するのが苦しそうにしていたのを覚えています。
口呼吸になっている人の特徴
長男が3歳くらいのとき、口呼吸かもと思っていたので、歯医者さんの定期健診の時に先生に口呼吸のサインはありますか?と聞きました。すると「気づくと口が開いていたり、寝ているときにいびきをかいたり、唇がいつも乾いている、上唇がめくれあがっている子は口呼吸の心配があるよ」と教えてもらいました。長男は口が開いていたり、寝ているときに時々いびきをすることがありました。先生によると「お口の体操で改善していくからやってみてね」と言われて、家族で取り組むきっかけとなりました。
なぜ口呼吸になるのか
我が家の長男は花粉症で、季節の変わり目や春先はいつも鼻づまりの症状がありました。保育園の先生に鼻づまりの時は苦しそうに口で息をしています。とお迎えの時言われました。そうか!口呼吸のきっかけはこれなのかもしれない!と思って耳鼻科に通院しました。耳鼻科の先生に「鼻が詰まっているときや、鼻水が多いときは口呼吸になるし、それが常態化すると、鼻水が止まっても口呼吸になってしまいますから、鼻水が出始めたら放っておかないで、薬できちんと鼻水を止めたり、鼻吸いで吸ってあげましょう。」とアドバイスをくれました。
また歯並びで口が閉じづらかったり、骨格で口が閉じづらい問題もあります。口周りの筋力がまだ未発達な子どもはちょっとしたきっかけで口呼吸になると保育園の先生から指導されました。
大人になっても患者さんで多いのはアレルギー性鼻炎があり、鼻呼吸が苦手な方です。歯をクリーニングする時に出るお水が口にうまく貯められない方が多いです。
また、スマホやパソコン作業が多く、無意識に口が開いてしまうというかたも多かったです。
口呼吸がもたらす体への影響
虫歯・歯周病・口臭のリスク増加
長男の花粉症がひどいときに、定期歯科健診に行ったときに、「口の中の乾燥がひどいですね。今は虫歯になっていなくても、虫歯になるリスクは圧倒的に高くなりますよ。」と言われて、歯みがきしていても虫歯のリスクは変わるんだと衝撃を受けました。
唾液は本来、細菌の繁殖を抑え、食べかすを洗い流して虫歯や歯周病を防ぐ役割があります。乾燥すると細菌が増殖しやすくなり、口臭も悪化します。虫歯・歯周病が進行しやすい環境です。
風邪や感染症にかかりやすくなる
鼻呼吸は、鼻毛や粘膜がフィルターの役割を果たし、ウイルスや細菌の侵入を防ぎます。しかし口呼吸では、これらの防御機能が働かず、直接喉や気管に病原体が入りやすくなります。また鼻腔を通り、気道に抜けるまでに空気が体温で温められて、新鮮な温かい空気が肺に充満します。肺を冷やさずに風邪予防ができます。
長男は口呼吸が多くなってきてからは、冬になると毎年のように喉風邪をひいていました。小児科の先生に「口呼吸だとウイルスが直接のどに貼りつき、口の中のばい菌と一緒に繁殖して体調崩しやすくなります。」特に朝起きたときの喉の痛みが強く、マスクをして寝ても変化なかったところ、口呼吸が改善し始めてから、喉の痛みや風邪の頻度が明らかに減ってきました。
顔つきや歯並びへの悪影響
口呼吸を続けていると、口周りの筋肉が使われずに衰え、顔のたるみやしわ、老けた印象を与えやすくなります。また、舌の位置が下がり、歯並びが乱れやすくなることも。
集中力や睡眠の質の低下
口呼吸は酸素の摂取量が低下し、脳への酸素供給が不足しがちです。その結果、集中力や記憶力が低下しやすくなります。また、睡眠時無呼吸症候群やいびきの原因にもなります。
我が家の長男も鼻水がひどいときは、口呼吸が1日中続きます。夕方になると頭がボーッとすると言って普段はしないお昼寝をするときがありました。
患者さんへの指導体験談:
仕事中に眠気や集中力の低下を感じることが多く、コーヒーでごまかしていたそうです。口呼吸を意識して改善してからは、頭がスッキリしやすくなり、仕事の効率もアップしたそうです。
今日からできる!口呼吸改善法
口周り・舌の筋力トレーニング(あいうべ体操)
歯科健診で言われたのが口の体操をして口の筋力を育てれば、口が閉じられるようになります!ぜひ毎日少しずつ続けてください!と紹介してくれました。そこから長男はじめ家族みんなでお風呂の時、取り組みました。
やり方:
-
「あー」と口を大きく開く
-
「いー」と口を横に広げる
-
「うー」と口を前に突き出す
-
「べー」と舌を下に突き出す
これを1日30回程度、毎日続けます。
患者さんの体験談:
最初は恥ずかしくて続けられるか不安でしたが、朝の洗顔後や夜の入浴後に習慣化。2週間ほどで口を閉じる力がつき、日中も口が開きにくくなりました。
私は運転中信号待ちの時にすることにしています。
よく噛んで食べる
食事の際によく噛むことで、口周りの筋肉が鍛えられます。ガムを噛むのも効果的です。早食いだった次男に、一口30回噛むことを心がけるように声掛けをしながら食事をしていました。顎や頬の筋肉がしっかり使われる感覚があり、食後の満腹感も満たされているようで次男もすすんで取り組んでいました。
口テープ・鼻呼吸テープの活用
寝ている間の口呼吸防止には、口テープや鼻呼吸テープが有効です。市販の医療用テープを縦に貼るだけで、口が開きにくくなります。
長男はひどく疲れているときは決まっていびきをかいて口が開いていました。口テープを貼って寝かせると最初は違和感がありましたが、慣れると朝の喉の乾燥や口臭が激減。家族から「いびきが減った」と言われ、長男もよく眠れる実感があるようでした。
舌の位置を意識する
正しい舌の位置は、上あごの前歯の付け根あたり(スポット)です。普段から舌が下がっていないか意識しましょう。
私の実践談:
デスクワーク中やテレビを見ているとき、ふと舌の位置を確認。意識して上あごに舌をつける癖をつけることで、最初は意識して舌を挙げていましたが、癖になってくると自然と口が閉じやすくなりました。
歯並びや骨格の問題は専門医へ
歯並びや骨格の問題が原因の場合は、歯科矯正など専門的な治療が必要です。
私の実践談:
歯並びの矯正を受けてから、口が自然に閉じやすくなり、口呼吸が減少しました。見た目の印象も大きく変わりました。大人の矯正は期間が長くかかりますが、見た目だけではなく機能面でも鼻呼吸ができるようになり自信が持てるようになりました。
体験談まとめ:口呼吸を改善して変わったこと
-
朝の喉の痛みや口臭が激減
-
風邪や喉の不調が減少
-
顔のたるみや口元の緩みが改善
-
集中力や睡眠の質が向上
-
歯医者でのトラブルが減った
まとめ
口呼吸は、虫歯や歯周病、口臭、風邪、顔のたるみや歯並びの乱れなど、健康と美容の両面に深刻な影響を及ぼします。しかし、正しい知識と毎日の小さな習慣の積み重ねで、誰でも改善が可能です。
私自身も、口呼吸の改善に取り組むことで体調や見た目が大きく変わりました。ぜひ、今日からできる方法を実践し、健康的で若々しい毎日を手に入れてください。
よくある質問Q&A
Q. 口テープは毎日使っても大丈夫?
A. 鼻づまりがない場合は毎日使用しても問題ありませんが、違和感や不快感が強い場合は無理せず中止し、医師に相談しましょう。
Q. あいうべ体操はどれくらいで効果が出る?
A. 個人差はありますが、2〜3週間続けると口を閉じる力がついたと実感する方が多いです。
Q. 子どもでも取り組める?
A. あいうべ体操やガムを噛むトレーニングは子どもでも安全に行えます。歯並びや顔つきへの影響が大きいため、早めの対策が重要です。
おわりに
「なんとなく」続けてしまっている口呼吸。しかし、そのまま放置すると健康や美容に大きなリスクが潜んでいます。
私の体験を通じて、少しでも多くの方が口呼吸の危険性に気づき、今日から改善に取り組んでいただければ幸いです。あなたの毎日が、もっと元気で美しくなりますように――。
(※本記事は体験談を含みますが、症状や改善法には個人差があります。気になる症状がある方は、歯科や耳鼻咽喉科など専門医への相談をおすすめします。)

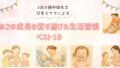
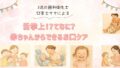
コメント